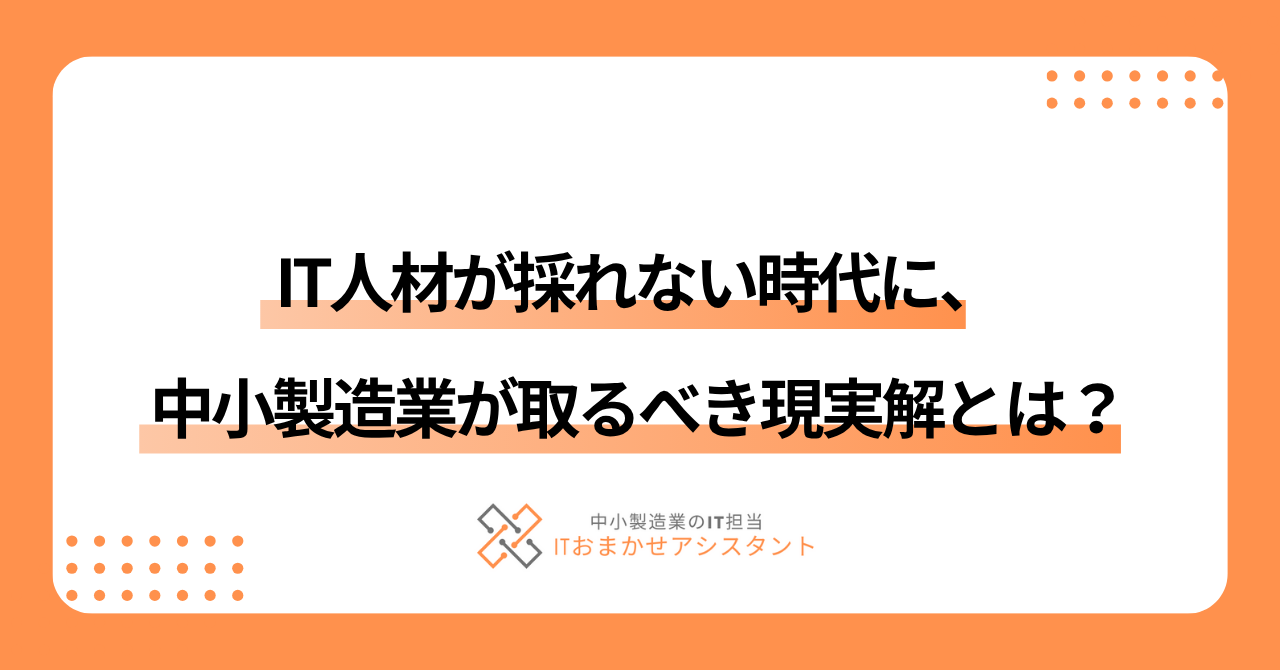目次
人が来ない、でも待ったなし
IT対応は待ったなし。でも、人が来ない――。そんな現場の焦りが静かに広がっています。
多くの企業が「IT人材を採用したいけれど採れない」という現実に直面しており、現場では頭を抱える毎日が続いています。
「ITに詳しい人が来ない」現場の悩み
「IT人材が欲しいのに、いい人材がまったく獲れそうにない」
そんな声が、特に中小企業の現場から多く聞こえてきます。
ITの重要性は年々高まっており、セキュリティ対策や業務のデジタル化、DX推進など、放置できない課題が山積みです。しかし現実には、「IT人材の給与が高すぎる」「募集しても人が来ない」「やっと来てもすぐに辞めてしまう」――そんな“採れない・定着しない”悩みを抱える企業が後を絶ちません。
IT業務は待ったなしなのに、手が足りない
業務システムの入れ替え、セキュリティ強化、データ整備など、IT業務は複雑化する一方です。しかも、社内の“誰か”がやらなければ、何も進みません。
「このままではまずい」とわかっていても、対応できる人がいない。現場はそんなジレンマに直面しています。
今こそ、現実的な解決策を考えるタイミング
この記事では、
✅ なぜ中小企業ではIT人材が採れないのか
✅ 社内で無理に兼任させる方法に限界がある理由
✅ 採用以外の選択肢とそのメリット
について、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
中小製造業で“採用できない”のはなぜ?
「応募が来ない」「定着しない」――その背景には、構造的な課題が潜んでいます。
中小製造業がIT人材を採用できない理由は、単に“人気がない”からではありません。見逃せない落とし穴がいくつもあります。
売り手市場が続くIT人材の採用環境
そもそもIT人材は今、どの業界からも引っ張りだこの状況です。大手企業やコンサル会社、ベンチャーなどが高待遇で積極採用を進めており、経験者ほど“選べる立場”になっています。
そのため、「より安定していて給与が高く、やりがいのある環境」を求める人材が、中小製造業にはなかなか目を向けないのが実情です。
中小企業が抱える4つの採用ハードル
中小企業のIT人材採用がうまくいかない理由には、以下のような壁があります:
✅ 給与や待遇の格差
大手企業やIT関連企業との年収差は大きく、待遇で勝負するのは厳しい状況です。
✅ 勤務地の不利
地方や郊外にある工場・本社では、通勤の問題で候補者が絞られてしまいます。
✅ キャリアパスが見えにくい
「この会社で成長できるのか?」という問いに明確な答えを出せないことも。
✅ 面接での“目利き”ができない
ITの専門性を持つ人が社内にいないため、スキルを見抜く力が足りないケースが多くあります。
教育・定着の仕組みも不足している
仮に採用できたとしても、受け入れ側の体制が整っていなければ定着しません。
IT業務の引き継ぎや教育を任せられる人材がいないため、入社後に孤立してしまい、早期離職につながることもあります。
採用できないのではなく、「仕組みがない」だけ
実は、「採用できない」のではなく「採用を機能させる仕組みがない」というのが根本的な問題です。
求人の出し方、面接の進め方、入社後のフォロー体制――これらを整えていないまま採用活動を行っても、空回りするばかりです。

代替案としての社内兼任|うまくいくのか?
採用が難しい今、現場では「社内の誰かに兼任してもらう」という選択が取られがちです。
一見、現実的な判断のように見えますが、そこには見過ごせない落とし穴があります。
「詳しそうな人にやらせる」現場の実情
採用が難しいからと、社内の誰かにIT業務を兼任させるケースはよくあります。
たとえば「パソコンに詳しいから」「若いからITに強そう」といった理由で、総務や経理、製造部門の社員がIT業務を任されることも珍しくありません。
兼任による3つの問題点
しかし、“なんとなくの兼任”には以下のようなリスクが潜んでいます:
- IT業務が後回しになる
日々の本業が優先されるため、トラブル対応が遅れがちに。 - 属人化によるブラックボックス化
担当者しか分からない状態になり、引き継ぎも困難に。 - 責任の所在が曖昧になる
「自分はIT担当のつもりじゃなかったのに…」という不満が生まれやすくなります。 - 評価が難しい
本業以外なので評価をどうするか、制度がないケースが多いので難しいです。
応急処置としては機能するが、限界も
もちろん、短期的な対応策として“兼任”という選択肢は有効です。
しかし長期的に見ると、属人化・非効率化・精神的ストレスといった課題が積み重なり、組織全体に悪影響を及ぼします。
中には、IT対応を担っていた社員が退職し、残された社員が何も分からず業務が完全にストップする――という事例も。
IT対応を「ついで仕事」で回すには、あまりにもリスクが大きすぎるのです。

他社はどうしている?採用以外の選択肢
「うちでは採れない」と割り切った企業ほど、すでに“次の一手”を打ち始めています。
人を雇うだけが正解ではない――。そんな考え方が、今や中小企業の間でも当たり前になりつつあります。
外部ベンダーをスポット的に活用する
もっとも多く見られるのが、必要なときだけ外部のIT業者に依頼するという方法です。
たとえば、PCの入れ替えやネットワークトラブルなど、単発の案件ごとに外注する形です。
一度にかかるコストは高めに見えますが、常駐の人材を雇うよりも安く済むケースも多く、コントロールもしやすいのが特徴です。とりあえずリスクに目をつぶって現状維持だけであればこれで十分です。
“ひとり情シス代行”のようなサービスを使う
近年は「社内にIT担当がいるように支援する」外部サービスも増えています。
特定の会社と契約し、日常的な問い合わせ対応や機器のトラブル対応などをリモートで支援してもらう形です。
「誰に聞けばいいのか分からない…」という状態から、「まずここに聞けば大丈夫」という安心感が生まれ、社内のストレスも軽減されます。
ハイブリッド型で対応する企業も
社員の中に多少なりともITスキルがある人がいれば、その人を“窓口”として立て、実際の実務は外部の専門家が担うというハイブリッド型も増えています。
「内と外」をうまく組み合わせることで、コストも抑えつつスピード感のある対応が可能になります。
採用できないからこそ、柔軟な体制へ
皮肉に聞こえるかもしれませんが、「採用できない」という前提があるからこそ、こうした選択肢を積極的に導入し、柔軟でスピーディな体制を作る企業が増えています。
“採れない”ことは、決して失敗ではありません。
むしろ、その現実を受け入れたうえで、別の形で課題を解決できる力こそが、今の時代に求められているのかもしれません。
解決策のひとつ|「ITおまかせアシスタント」
人材を採用せず、教育も不要。それでも“ITの不安”を手放せる方法があるとしたら?
そんなニーズに応えるのが、「ITおまかせアシスタント」です。
経験豊富な人材を“チーム”で提供
「ITおまかせアシスタント」は、社内にIT担当者がいなくても、専門的な対応ができるように設計されたサービスです。
最大の特長は、「ひとりを採用する」のではなく、「チームで支援する」点にあります。
クラウドのソフトウェア、サーバーやネットワーク、PC設定など、それぞれの専門分野に長けたスタッフが連携して、必要なときに必要な支援を提供します。
業務改善を伴うIT化の企画や支援に対応
避けられないIT化に対応するために、ITの企画、IT導入に向けた業務改善、IT導入などをIT担当の代役として伴走します。中小製造業はIT導入に失敗することも多いですが、かなりの確率で失敗を避けられ、業務がシンプルになります。
社員からの問い合わせにも対応
ITに詳しくない社員からの「これってどうすればいいの?」という質問にも、気軽に対応してもらえるのが大きな安心材料。
ヘルプデスクとして、日常的な相談窓口を設けることで、社内の混乱やストレスを未然に防ぎます。
たとえばこんな対応が可能です:
✅ PCやプリンタの不具合対応
✅ ソフトウェアに関する質問対応
✅ 新入社員のキッティング作業
✅ ベンダーとのやり取り代行 など
「ここに聞けばOK」がある安心感
「ITのことはここに聞けば大丈夫」――そう言える体制があるだけで、社員の心理的負担はぐっと減ります。
わからないことを誰に聞けばいいか分からず、作業が止まってしまう…という事態を防げるのです。
明確な料金体系で安心
コスト面でも「うちは無理」と思われがちですが、実は明確な料金体系と必要に応じたプランで、無駄なく導入できるのも魅力のひとつです。
「人を雇うほどでもないけれど、今のままでは不安」
――そんな企業にこそ、ぴったりの仕組みと言えます。
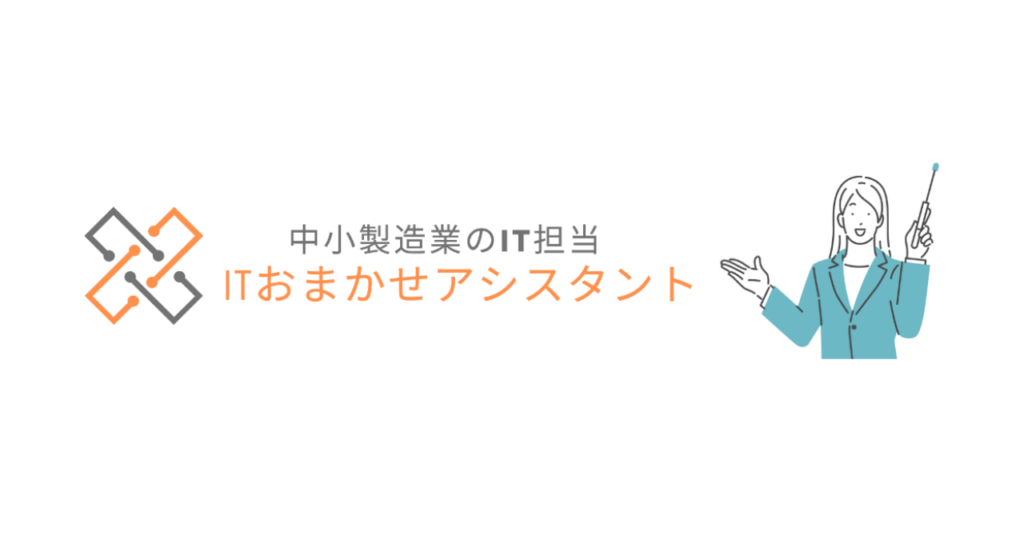
まとめ
IT人材が採用できない状況は、もはや多くの企業にとって当たり前の課題になりつつあります。そんな中で重要なのは、「人を雇う」ことに固執せず、今あるリソースでどう支えるかを考える視点です。
社内で無理に兼任させるやり方では限界がありますし、育成にも時間とコストがかかります。だからこそ、“最初からできる人に任せる”という考え方が現実的な選択肢になります。
外部の力をうまく取り入れ、社内に「ITのことはここに聞けば大丈夫」という状態をつくることで、日々の業務も、いざというときも止まらなくなります。
採用が難しい今だからこそ、仕組みで乗り切る――その一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
「ITおまかせアシスタント」では、貴社の状況に合わせて、無理のないスタートをご提案いたします。
ちょっとした不安、現状の整理、料金のことまで、どんなことでもお気軽にお尋ねください。