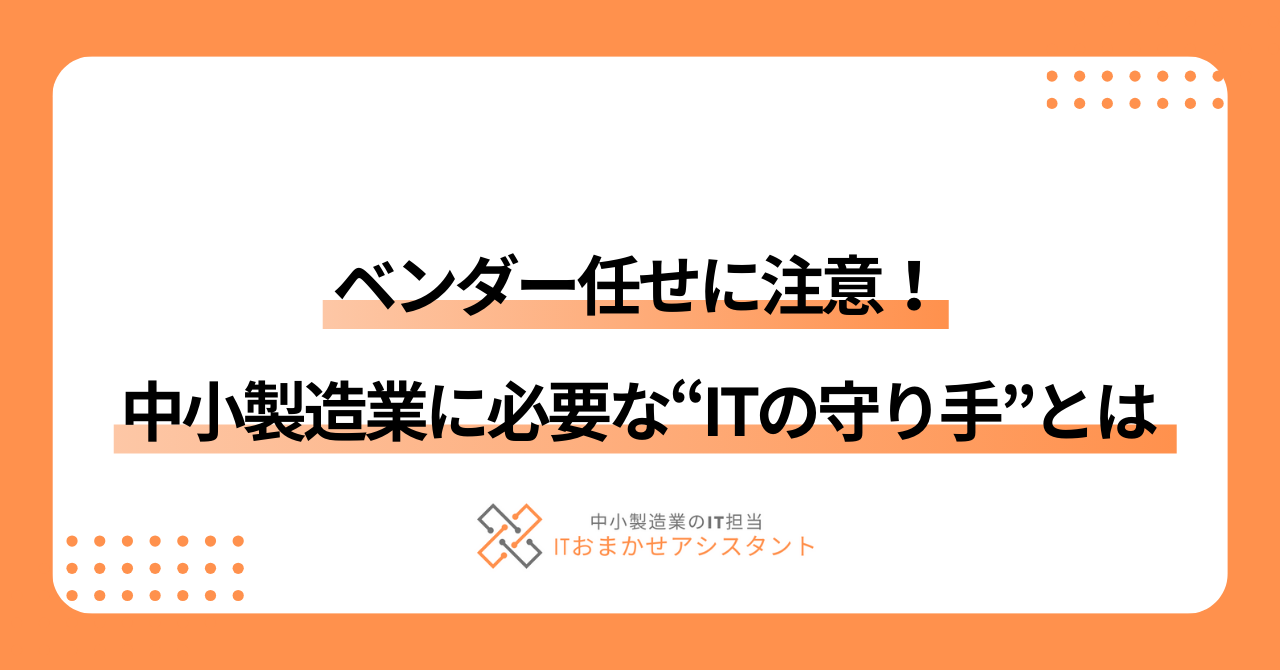目次
情シス業務、丸投げしていませんか?
「ITのことは全部、外部の業者に任せているから大丈夫」
そんな状態になっていませんか?
たしかに、社内に専門の人材がいない場合は、外部に頼るのが自然な流れです。
ですが、“すべてを丸投げ”するのは、見えないリスクを抱える行為でもあります。
⚠️ トラブル対応に時間がかかる
⚠️ 社内にITの知識が蓄積されない
⚠️ 業務に合わない高額システムを導入してしまう
そして何より、自社のシステムを他社に握られることで、将来的に身動きが取れなくなる危険も。
この記事では、情報システム業務の丸投げが引き起こすリスクと、
安全・安心なIT運用を実現するための考え方を分かりやすく解説します。
情報システム業務とは?会社を支える“ITの守り手”
「情シス(情報システム)業務」とは、
簡単に言えば、会社のIT環境を整え、安定して使えるようにする仕事です。
見えづらい存在ですが、会社のインフラを裏で支える重要なポジションです。
情シス業務の主な内容:
- 企画:どんなITツールやシステムを使うかを検討
- 導入:パソコンやネットワーク機器の設定や設置
- 管理:セキュリティ対策、バックアップ、トラブル対応など
これらがきちんと行われていれば、業務はスムーズに進みます。
📌 請求書が出せる、📌 データが守られる、📌 メールが届く
――それはすべて、情シス業務が整っているからこそ。
つまり、情シス業務は「会社を止めない」ための要の存在です。

情シス業務をベンダーに丸投げすると?
社内に詳しい人がいないという理由で、
情シス業務をすべて外部ベンダーに任せているケースは多くあります。
しかし、丸投げ状態が続くと、以下のような問題が発生します。
⚠️ トラブル対応に時間がかかる
ネットワークトラブルや印刷の不具合など、
緊急時にベンダーの対応待ちで業務がストップしてしまうケースも。
⚠️ 社内にノウハウが蓄積されない
日々の運用をすべて外注していると、
「このパソコンはどう設定されているのか」
「ネットワーク構成はどうなっているのか」
といった基本情報すら把握できなくなります。
⚠️ 業務に合わないシステムを導入してしまう
ベンダーから提案された内容をそのまま受け入れて、
高額なパッケージや、使いにくいシステムを契約してしまう例も。
⚠️ ベンダーに“会社の命綱”を握られる
最も深刻なのがこれです。
システム設計や設定がすべて外部任せだと、
「誰も内容を把握していない状態」が生まれます。
その結果…
- 担当者が退職した途端、対応不能
- 契約を切りたくても、移行ができない
- 提示された金額を断れず、言いなりになる
📌 IT環境は、今や会社の根幹です。
それを“他人任せ”にしてしまうのは、経営的にも危険な判断です。
情シス業務をベンダーに完全に任せてしまうと、トラブル対応の遅れやノウハウの欠如、高額契約のリスクなど、気づきにくい依存状態が生まれます。
そして最も怖いのは、自社の業務基盤であるIT環境を「自分たちでコントロールできない」状況に陥ること。
ITはもはや、製造業にとっても不可欠な経営インフラです。
“任せる”と“丸投げする”は全く別物。
守り手不在の状態は、いずれ大きなコストや信用の損失につながりかねません。

丸投げが引き起こす具体的なリスク
情シス業務を外部に任せること自体が悪いわけではありません。
問題は、「社内で何も判断できない」「全てをベンダー任せにしている」状態が常態化してしまうことです。
この体質が続くと、次のようなリスクが現実に起こります。
⚠️ 不要な高額システムを契約してしまう
ベンダーが提案するままに契約し、実際にはほとんど使われていない機能がある、というケースは少なくありません。
使いこなせていないのに、高額な保守費用を毎年払い続けている企業も見られます。
⚠️ システム保守で“首根っこを掴まれる”
業務に欠かせないシステムの保守が特定の業者に依存していると、対応を急いでも「混み合っていてすぐには行けません」と言われることも。
また、「仕様が複雑なので他社では対応できません」と言われ、乗り換えもできない状況になることがあります。
⚠️ 古くなったシステムがそのまま使い続けられる
長年使ってきたシステムを入れ替えようと思っても、
中身の仕様がわからない、設計資料が残っていない、といった理由で作業が進まないことがあります。
また、「このシステムを作った業者にしかわからない仕組みになっていて、他社には頼めない」といった属人化もよくあるケースです。
結果として、古くて使いにくい仕組みを“仕方なく”使い続けるしかなくなる。
業務に合わない状態が続いたり、セキュリティの面でもリスクが増える可能性があります。
実際、中小企業のITトラブルの多くは「自社で把握していなかった」「確認できる人がいなかった」ことに起因しています。
ベンダーとの関係が悪化したときや、担当者がいなくなったときに業務が止まってしまうのは、大きな経営リスクです。
自社で何も判断できない・変えられない状態を放置すると、自由度も交渉力も失い、将来的な選択肢が狭まっていきます。

なぜ「社内にITのわかる窓口」が必要なのか?
「全部わかる人がいないから外注している」
その考え方自体は間違いではありませんが、社内に“最低限のわかる人”がいるかどうかで、ITの運用体制は大きく変わります。
✅ ベンダーとのやりとりを円滑にできる
要件を正確に伝え、提案内容をある程度理解できる人がいることで、無駄なやり直しや不要な機能の押し売りを避けられます。
✅ トラブルの一次切り分けができる
ネットがつながらない、システムがトラブった、といったときに、簡単な確認や聞くべきベンダーの特定などの初期対応をできる人がいるだけで、復旧スピードが段違いです。例えば、インターネット接続トラブルの場合、PCの設定・セキュリティソフト・ルーター等機器・プロバイダ(インターネット回線業者)でたらい回しになることもあります。
✅ 意思決定を社内で行える
IT投資の判断や運用方針などを外部任せにせず、社内で検討できる体制が整っていれば、“自分たちのIT”として主体的に運用することができます。
💡 すべてのITを理解している必要はありません。
重要なのは「わからないことを、誰にどう聞くか」がわかっている人がいることです。
社内にITの窓口となる人がいなければ、何を選ぶか、何を変えるかの判断もベンダー任せになります。
それでは、自社にとって本当に必要なIT環境は整いません。
最低限のIT知識を持つ“橋渡し役”が、これからの時代の必要条件です。

とはいえ、社内だけでは回せない現実も
理想は、社内にITを理解する担当者がいて、自前で判断・管理できる状態です。
しかし現実には、それが難しい企業も多くあります。
⚠️ IT専任担当を置く余裕がない
中小製造業では、人数も限られ、専任の情シスを雇うだけのコストが出せないというケースが大半です。
実際、総務や経理がIT対応を“ついでにやっている”こともよくあります。
⚠️ 社内に広くITをわかる人材がいない
ネットワーク、セキュリティ、業務システムなど幅広い知識が求められる中で、
「全体を把握できる人」はなかなか育ちにくいのが現状です。
⚠️ IT人材の採用が難しい
仮に専任を雇おうとしても、IT人材の採用は都市部でも競争が激しく、給与も高いです。
地方や中小企業にとってはハードルが高すぎるという声も多く聞かれます。
ITの重要性はわかっていても、体制が追いつかないのが今の多くの中小企業の現実です。
だからこそ、社内だけで何とかしようとするのではなく、“外部の力をうまく借りる”発想がカギになります。
そんなとき頼れるのが「 ITおまかせアシスタント」
社内にIT人材を置けない。でも丸投げもリスクが大きい。
そのジレンマを解決するのが、「 ITおまかせアシスタント」です。
📌「 ITおまかせアシスタント」は、単なる“外注”ではありません。
「社内のIT担当者が隣にいる感覚」で、伴走しながら支援するサービスです。
✅ 小さなITの悩みもすぐ相談できる
「パソコンの調子が悪い」「メールの設定がわからない」
そんな日常のトラブルから、丁寧に対応。現場で困ったときに、すぐに頼れる存在になります。
✅ IT環境の見直し・最適化を提案
現在のシステムが業務に合っているか、ムダなコストがかかっていないか。
第三者の目線でチェックし、業務に合った現実的なIT環境づくりをサポートします。
✅ ベンダーとのやりとりも代行
複数の業者と契約していると、それぞれとやりとりするのは大きな負担です。
「 ITおまかせアシスタント」は、“通訳役”として間に立ち、交渉や調整も代行します。
✅ コストも透明化・適正化
ITに詳しくないと、契約内容や料金の妥当性もわかりません。
不要な契約を洗い出し、本当に必要なものだけを残すコスト最適化を行います。
💡 特徴は、ただやってくれるだけでなく、「一緒に考えてくれる」こと。
システムも、セキュリティも、トラブルも、「自分たちのIT」として主体的に動ける体制を整えます。
📌任せながら“自社の判断力”を育てるパートナー
「 ITおまかせアシスタント」は、単なるアウトソーシングではなく、
“ITの守り手”として、御社の隣で支える伴走者です。
必要なときに必要なことを、分かりやすくサポートしてくれる、まさに“ちょうどいい”ITの味方です。
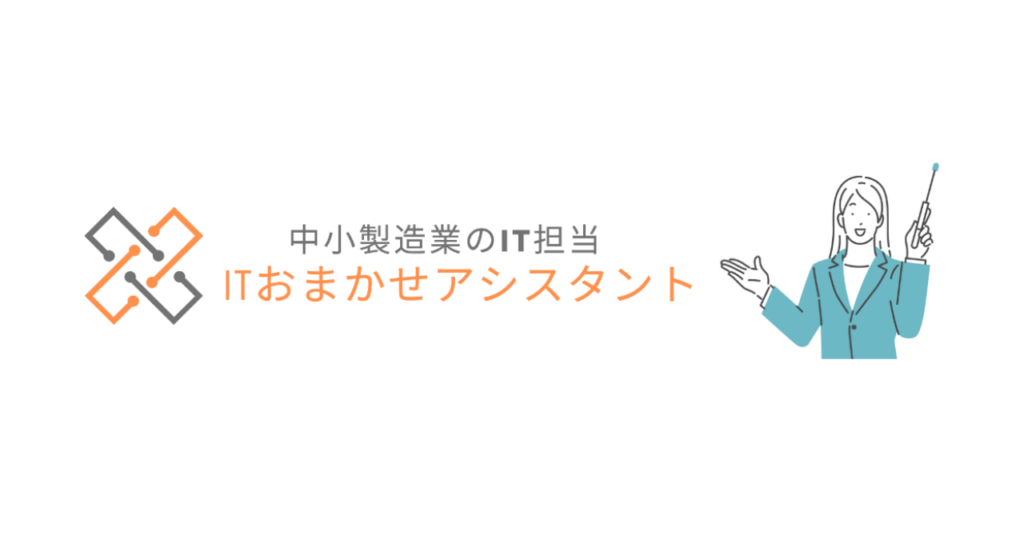
「 ITおまかせアシスタント」導入事例
ここでは、実際に「 ITおまかせアシスタント」を導入して改善した事例をご紹介します。
🧾 事例:製造業A社(従業員20名・部品加工)
A社では、社内のIT環境を長年大手ベンダーに一任しており、
ネットワーク障害やパソコンのトラブルが発生しても、対応はすべて業者任せの状態でした。
⚠️ 「メールが送れない」「サーバーにアクセスできない」といったトラブルが起きても、
そのたびに業者の到着を待つしかなく、生産や事務業務が何度もストップしていました。
💡 そこで「 ITおまかせアシスタント」を導入。
高額な保守契約を整理し、年間で約25万円のITコスト削減を実現しました。
普段のトラブルにも即対応してくれる体制が整い、
従業員からも「誰に相談すればいいかが明確で安心できる」という声が多く上がりました。
今では、新しいシステム導入やセキュリティ対策も、「 ITおまかせアシスタント」と一緒に検討しながら進めており、「自社のITを“自分たちで考える”意識」が生まれたとのことです。
🧾 事例:製造業B社(従業員50名・鋳造業)
B社では、これから社内のIT化を進めようとしており、中小機構や商工会議所に相談していました。
⚠️ 何度も専門家を紹介してもらって業務分析や要件定義を行いましたが「なかなか進まない」「本当に最新の情報か疑問」と感じていました。実際に紹介されたベンダーは技術力が怪しいところでした。
💡 そこで「 ITおまかせアシスタント」に相談。
状況を確認したところ、業務が複雑すぎてシステムをすぐに入れると大変になることが判明。大まかなシステムの方向性を示しつつ、まずは業務改善を進めることにしました。
まずは受発注の業務を標準化。現在はシステムを導入中で、それが終わったら生産管理業務の標準化を進める計画です。
受発注の担当者からは「手書きとFAXだらけで毎日残業でしたが、残業はかなり減りました。」との声が聞かれています。
受発注システムの担当者として社内メンバーを育成しつつ、生産管理等も含めたトータルのシステム構想は「 ITおまかせアシスタント」が担う、といった「自社のITを任せっきりにしない」ようにしながら「スキルが不足している部分を委託する」という体制を築いています。
📌 頼れるパートナーがいるだけで“ITに強い会社”になれる
「 ITおまかせアシスタント」の導入で、業務の安定性が高まり、経営判断にも余裕が生まれたとA社は実感しています。
トラブルを未然に防ぎ、ITのことを気にせず仕事に集中できる環境が整いました。

情シスの“守り手”が会社を強くする
情報システム業務の丸投げは、目に見えないリスクを育てます。
依存状態が続けば、いざというときに何もできず、コストもコントロールできません。
✅ これからの企業には、「わかる人が社内にいること」と、
「わかってくれる外部パートナーがいること」が両方必要です。
💡「 ITおまかせアシスタント」は、まさにその“ちょうどいい守り手”。
情シスの負担を軽くしながら、自社の判断力も育ててくれる存在です。
「ITに困らない会社」は、それだけで仕事に集中でき、成長も早まります。
自社に合ったITのあり方、今こそ見直してみませんか?
ITに関してのお困りごとがあればご相談ください。