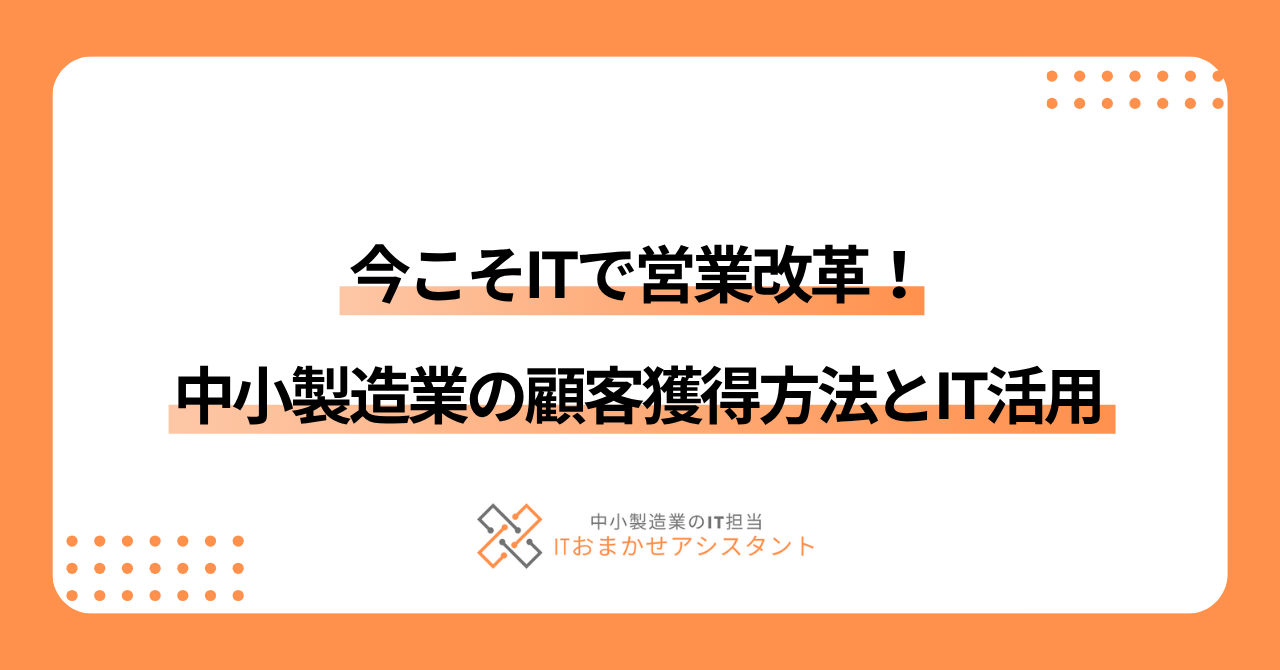目次
なぜか、最近営業がうまくいかない
技術には自信がある。昔は紹介だけで仕事が途切れなかった。それなのに、ここしばらくは問い合わせが減り、展示会の反応も薄くなってきた。そんな声を聞く機会が増えています。
営業担当は毎日フル稼働。顧客対応や見積り作成、製造との調整で、1日があっという間に過ぎていく。
新規営業と社内フォロー、顧客対応、どれかの優先順位を下げざるを得ない状況です。。
たとえば、こんな場面。
見積りを出してそのまま。「その後どうなりましたか?」と確認しないうちに、競合に流れてしまった。
誰かが担当変更になったら、過去の履歴が分からなくなる。営業資料も人によって管理方法がバラバラ。
これでは商談の流れが見えず、信頼を積み上げにくいのも当然です。
多くの会社で「営業が弱い」と言われる背景には、
個人の問題ではなく情報が整理されていない組織構造的な課題があります。
顧客情報、見積り、取引履歴──それぞれが個人の中で完結し、
会社全体どころか事務担当ですら把握できていないのです。
営業担当がどれだけ頑張っても、情報がつながらなければ成果は続きません。
必要なのは、「人を変えること」ではなく「仕組みを整えること」。
情報がバラバラな状態をつなぐだけで、営業のスピードも信頼度も大きく変わります。
つまり、営業がうまくいかない理由はスキル不足ではなく、
情報が点で止まっていること。
裏を返せば、情報を「見える化」し、チームで共有できれば、
営業の手ごたえは確実に変わるということです。
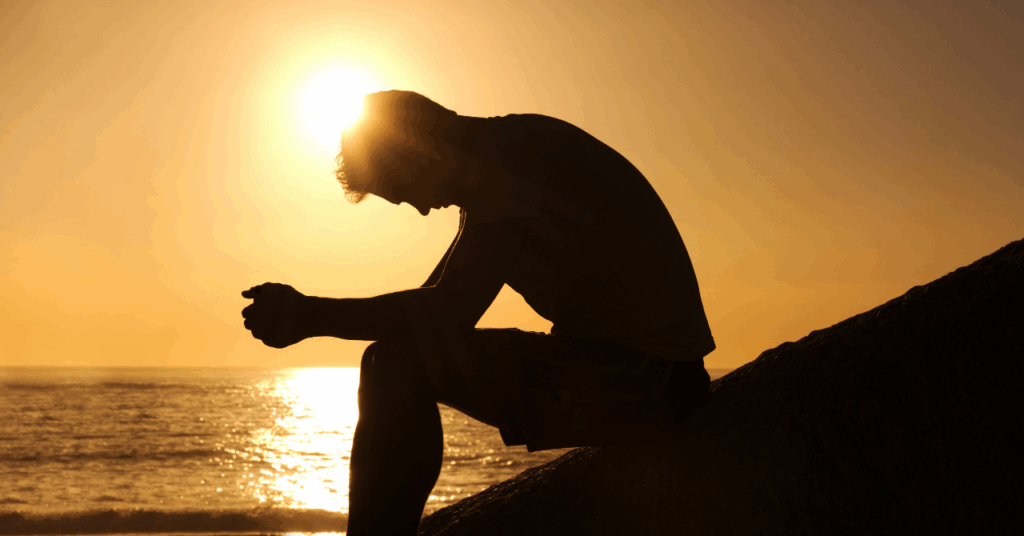
営業が空回りする構造──製造業特有の事情とは
中小製造業の現場では、営業専任がいない会社が珍しくありません。社長や技術者が製造と営業を兼任しており、「営業は時間がある時にやる仕事」になりがちです。
毎日、図面確認・見積り作成・納期調整…。現場が優先され、営業に十分な時間を割けません。結果、問い合わせ対応に追われて「受け身の営業」が続いてしまいます。
属人的な管理も、空回りの原因です。
✅ 見積りの出し方が人によって違う
✅ 顧客リストが個人PCの中にある
✅ 案件の進捗が共有されない
担当が変わるたびに関係がリセットされ、せっかく築いた信頼が途切れてしまいます。
さらに、「技術が良ければ自然に売れる」という考えも根強く残っています。以前は口コミや紹介で十分に仕事が回っていたかもしれません。
しかし、今の顧客はまずインターネットで情報収集を行い、複数の会社を比較してから問い合わせをしています。
技術が良くても、発信しなければ選ばれない時代になったのです。
それでも、
・ド新規の営業は苦手だから紹介に頼る
・広告はよくわからないし、お金がもったいない
・ホームページは作ったけど更新していない
という会社は少なくありません。
⚠️しかしその間に、他社はWebで実績を発信し、検索から見つけてもらっています。
「うちは営業が弱い」と感じている会社ほど、情報発信が止まっているケースが多いのです。
つまり、営業がうまくいかないのは「頑張り方」ではなく「仕組み」の問題。
営業を助ける情報の流れが整っていないから、努力が結果に結びつかないのです。
営業担当が頑張るよりも先に、情報を「見える化」し、共有できる状態を整える。
それが、製造業の営業改革のスタートラインです。
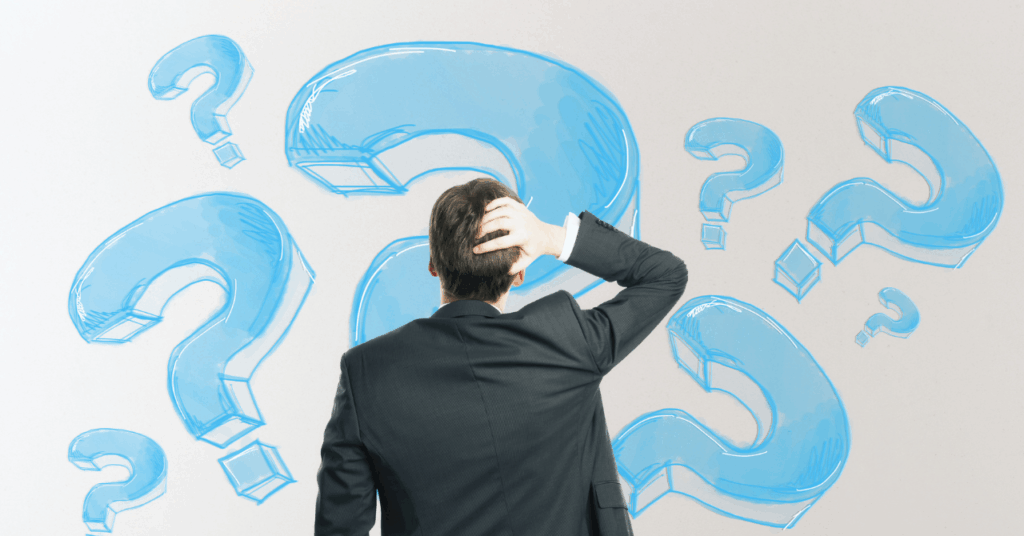
営業下手ではなく、仕組みがないだけだった
営業がうまくいかないと「うちは営業が苦手だから」と考えてしまいがちですが、
実はそうではありません。
多くの場合、課題は「人」ではなく「仕組み」にあります。
たとえば、こんな場面。
✅ 顧客から問い合わせが来ても、過去の提案内容や納期がすぐに分からない。
✅ 製造に確認してから返信するため、回答が遅れがちになる。
✅ メールや図面が個人管理で、どこに何があるか探しにくい。
現場も悪気はなく、情報がバラバラだから対応に手間がかかってしまうのです。
多くの中小製造業では、情報が点在しています。
名刺は机の中、メールは個人フォルダ、見積りはパソコンごとに保存場所が違う。誰かが抜けたら、取引履歴が追えない。
これでは「誰が・何を・どこまで対応したか」が見えず、フォロー漏れや行き違いが生まれてしまいます。
また、営業と製造の間にある「情報の壁」も大きな課題です。
営業が納期を聞いても、現場の進捗をすぐに把握できない。製造からの修正連絡が営業に届かず、顧客との認識にズレが生じる。
ほんの小さな連携ミスが、信頼の低下につながることもあります。
💡とはいえ、ここで知っておいてほしいのは「仕組みを整えるのは難しいことではない」という点です。
小さな会社ほど、変化の効果がすぐに現れます。全員の距離が近く、情報を共有しやすいからです。
たとえば、次のような工夫からでも十分です。
✅ 名刺をスキャンして顧客データを共有
✅ 案件ごとにフォルダを整理して見積り履歴を残す
✅ 製造実績を写真付きでまとめ、提案資料として活用
✅ 案件の進捗をオンラインで共有できるExcelのような表(Googleスプレッドシートなど)で見える化
どれも「高価なシステム」ではなく、今あるツールや比較的安価なサービスを使って整理するだけの取り組みです。
📌営業を強くするとは、営業担当を鍛えることではなく、営業が動きやすい仕組みを作ること。
これが整えば、属人的な営業から脱却し、チームで成果を出せるようになります。
ITは特別なものではありません。
💡日々の仕事を少しラクにする「便利な道具」として使えばいいのです。営業下手ではなく、営業を助ける仕組みがないだけ。その一歩を踏み出すことが、営業改革の本当の始まりです。
現場の声から生まれた、小さな改善の積み重ね
営業改革と聞くと、大がかりなシステム導入を想像する人も多いかもしれません。
でも、実際に成果を上げている会社の多くは、ほんの小さな工夫から始めています。
ここでは、現場のリアルな改善例を紹介します。
名刺をスキャンしただけで、情報共有がスムーズに
ある部品加工会社では、営業担当がそれぞれ顧客名刺を管理しており、担当交代のたびに「このお客様、どんな案件だったっけ?」と探すのが一苦労でした。
そこで、名刺をスキャンし、クラウド上で共有する仕組みを導入。
スマホから顧客情報をすぐ検索できるようになったことで、出先でも前回の打ち合わせ内容を確認できるようになりました。
📌担当が変わっても会話がつながり、「話が早くて助かる」とお客様からの信頼もアップ。
ITを入れたというより、「整理整頓をデジタル化した」だけの改善です。
過去の見積りを探しやすくして、対応スピードを向上
別の製造業では、見積書が担当者ごとにパソコンに保存されており、誰かが休むと他の人が対応できないという課題がありました。
営業チームは、見積書を案件名+顧客名で統一管理し、共有フォルダに整理するルールを設定。
検索で過去の案件を一瞬で見つけられるようになり、問い合わせへの回答スピードが格段に上がりました。
📌「前に出したあの仕様、すぐ見つかる?」という焦りがなくなり、営業全体のリズムが整ったのです。
ツールは特別なものではなく、社内の既存クラウドだけ。でも、それだけで日々の手間が驚くほど減りました。
製造実績を見せるだけで、営業トークが不要に
ある金属加工メーカーでは、製品をうまく説明できず、営業担当が「とにかく現場を見てください」と言うしかありませんでした。
そこで、製造実績の写真を社内でまとめ、シンプルなカタログ形式にしてタブレットで見せるようにしたところ、説明の時間が短縮され、提案の精度も上がりました。
📌お客様は「こんな加工もできるんですね」と驚き、新たな受注につながった例もあります。
「営業が話す」から「見せて伝える」へ。資料1つで印象が大きく変わったのです。
スマホで納期確認、商談がスムーズに
さらに、社内の製造進捗をGoogleスプレッドシート(オンラインで共有できるExcelのようなもの)で共有した会社では、営業が出先からスマホで納期を即答できるようになりました。
これまでは「工場に確認してから連絡します」で終わっていたところが、リアルタイムに答えられるようになり、商談成立率も上がりました。
📌「営業力が上がった」というより、現場と営業の距離が近づいたことでスピード感が生まれたのです。
こうした事例に共通しているのは、どれも大きな投資をしていないこと。
名刺スキャン、フォルダ整理、進捗共有──。
どれも「できる範囲の改善」を少しずつ積み重ねただけです。
📌ITは高価なシステムではなく、「便利な文房具」のように使えばいい。
無理をせず、自社のやりやすい方法で整理していく。それが一番現実的で、継続できる形です。
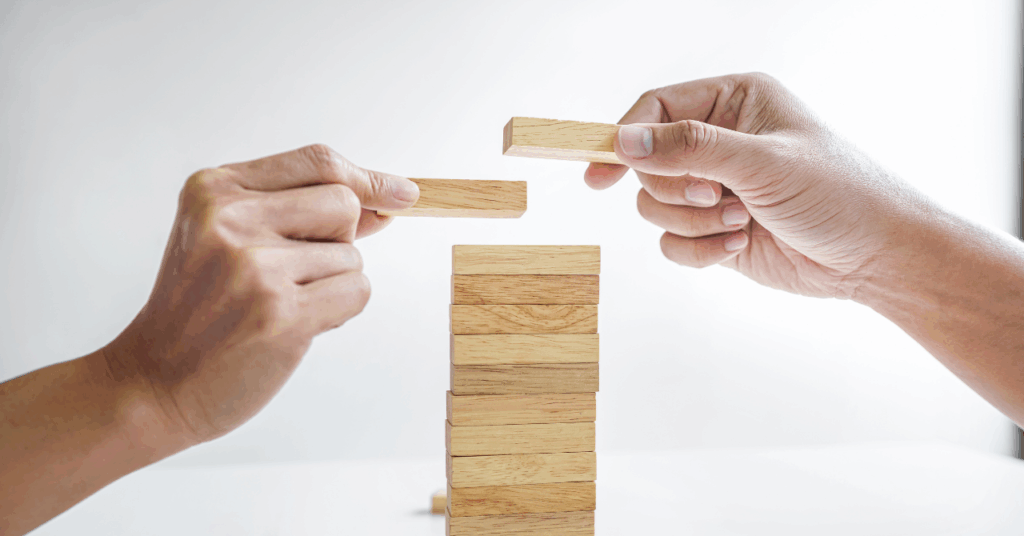
すべてはできなくていい。一つ整えるだけで変わる
営業改革と聞くと、「すべてをデジタル化しなければならない」と思いがちです。
しかし実際は、すべてを一度に変える必要はありません。
まずは、自社の中で「今いちばん困っていること」をひとつ整えるだけで、
営業の流れは見違えるほど変わります。
📌たとえば、営業資料のフォーマットを統一するだけでも効果は大きいです。
担当者ごとに異なる見積書や提案書をそろえることで、見やすく・比較しやすくなり、社内の確認もスムーズになります。
「これ、どの資料が最新?」というやり取りが減るだけでも、時間のロスは大幅に減ります。
整った資料はお客様にも安心感を与え、信頼につながります。
もう一歩進めるなら、製造実績の共有です。
製造の現場で撮った製品写真や事例を社内で見える化しておくだけで、営業は「どんな加工が得意か」をすぐ説明できるようになります。
「この事例のように、御社の部品も対応できます」
そんな一言で、商談の説得力がぐっと増すのです。
💡実績が共有されることで、営業の「説明力」が自然と上がる。それは「営業トークを磨く」よりも現実的で、効果の大きい改善です。
もちろん、どの会社にも限られた人手と時間があります。
だからこそ、小さな整備を一歩ずつ積み上げることが重要です。
まずは、できる範囲で「共有フォルダを整える」「打ち合わせメモをまとめる」。難しい部分は外部に頼る。
完璧ではなく、「継続できる仕組み」を目指すことが成功の近道です。
ある社長は、最初に「名刺共有」だけを整えました。それだけで顧客対応のスピードが上がり、
「他の仕組みも整えたくなった」と話します。ひとつ整えると、仕事の流れが変わり、社員の意識も前向きになる。
それが次の改善へのエネルギーになります。
✅完璧を求めるより、まず「整えることを続ける」こと。
これが、営業改革を現実的に進める最大のポイントです。
整備が積み重なると、
・引き継ぎがスムーズになる
・顧客対応が早くなる
・社員同士の会話が増える
──そんな変化が自然に起こります。
営業が「頑張る」ものから「自然に回る」仕組みへ。
それは、大きな投資ではなく、日々の小さな積み重ねから生まれます。
仕組みで営業を助ける時代へ
製造業における営業の悩みは、「人が足りない」「営業が苦手」「時間がない」など、どの会社でも共通しています。
けれど、その多くは仕組みで解決できる時代になりました。
営業担当を増やさなくても、情報の流れを整えるだけで成果が変わります。
📌これまで見てきたように、名刺をスキャンして共有する、見積りを整理する、製造実績を見せる。
たったそれだけの改善で、「対応が早くなった」「引き継ぎがスムーズになった」といった変化が生まれます。
それは、個人の頑張りではなく、仕組みが人を助けている証拠です。
これからの営業は、「感覚」ではなく「見える化」。
営業の流れを数字や情報で可視化できれば、どこにムダがあるか、どこを改善すればいいかが自然に見えてきます。
そして、現場の声を反映しながら小さく整えていく。
その積み重ねこそが、今の時代の「強い営業」の形です。
また、営業を支える仕組みづくりは、会社の文化を変えるきっかけにもなります。社員同士が情報を共有するようになれば、「誰かの課題は、みんなの課題」へと意識が変わります。属人化していた仕事がチームプレーに変わり、自然と「協働」が生まれていくのです。
技術や品質が良くても、売れなければ意味がありません。営業の苦手意識を責めるのではなく、仕組みで支える。それが、これからの中小製造業に求められる考え方です。
営業担当を増やすより、仕組みを整えて全員で動ける体制を作る。
それが、次の時代の「営業力」になります。
営業を頑張る時代から、営業が回る時代へ。
無理をせず、できるところから整えることで、会社全体が少しずつ前に進み始めます。
その最初の一歩は、特別なツールではなく、「困っていることを言葉にすること」。
そこから、仕組みづくりは必ず始まります。
まずは、「一人で抱え込まない仕組み」を持つことから始めてみませんか?
「ITおまかせアシスタント」では、貴社の状況に合わせて、無理のないスタートをご提案いたします。
ちょっとした不安、現状の整理、料金のことまで、どんなことでもお気軽にお尋ねください。