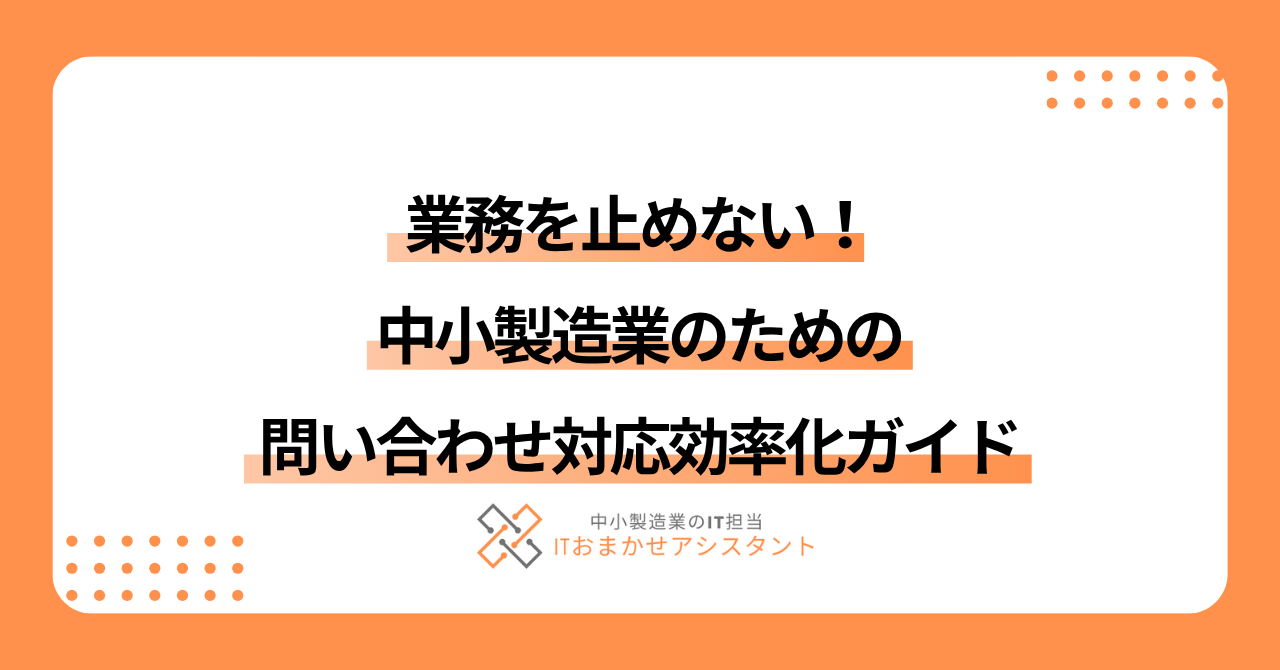目次
中小製造業を支える“縁の下の力持ち
:ヘルプデスク”が限界に
まずは、現場を支える“問い合わせ対応の現場”に目を向けてみましょう。
製造現場で「パソコンが動かない!」「プリンタが印刷できない!」といった声が上がるたびに、すぐに駆けつけて対応(=ヘルプデスク業務)しているのが社内のIT担当者です。
中小製造業ではこの役割を、専門部署ではなく、総務や生産管理担当、開発担当が担っているケースが少なくありません。
業務用PCや社内ネットワーク、プリンタ、業務システム、さらにはIoT機器のトラブルまで――あらゆる「困った」に対応するのが、現場の“縁の下の力持ち”であるIT担当者たちなのです。
ところが近年、問い合わせ件数の増加や技術的な複雑化により、「もう回らない」という声があちこちで聞かれるようになってきました。
本記事では、ヘルプデスク業務を担う社内のIT担当者たちが限界に陥っている背景と、その負担を減らして業務を止めないために、経営層が今すぐできる具体策をわかりやすくお伝えします。
なぜ中小製造業のヘルプデスク業務はここまで大変なのか
問い合わせ対応が限界に達している理由は1つではありません。複数の負荷が重なり、IT担当者の業務を圧迫しています。
① 幅広い業務をすべて担当している
中小製造業では、IT担当者がいないことも多く、社内で一番詳しい人が“ITっぽいこと全部の問い合わせ”をなんとなく引き受けている状況がよくあります。
パソコンの設定、Wi-Fiの不調、システムエラー、設備の通信エラーまで…。
「ITっぽいことは全部その人に頼む」が当たり前になっており、日常的に対応している業務量は想像以上です。
② あちこちからの問い合わせで優先順位がつけづらい
「急ぎでお願い」「とりあえずこれだけ」
――そうした依頼が、製造・営業・開発・経理など全方位から飛んできます。
特にITの運用ルールが決まっていない企業では、口頭や電話での“突発的な問い合わせ”が多く、対応記録も残らないため、後から何をどこまでやったのか把握しにくく、対応漏れも起きやすいという課題があります。
③ 製造業特有の“即時対応プレッシャー”
製造現場では、1分でもラインが止まれば損失につながるため、現場からの問い合わせは常に“今すぐ対応”が求められます。
対応するIT担当者は、複数の依頼を同時にさばきながら、優先順位を即座に判断する必要があるため、精神的にも非常にハードです。
④ ITリテラシーの差による“教える工数”
「USBが使えない」「エクセルが保存できない」など、初歩的な質問に毎回付き合わなければならないのもヘルプデスクの現場ではよくある話です。
一度説明しても同じ質問が繰り返されることも多く、“トラブル対応”ではなく“教育”に近い業務も発生しています。
こうした業務は、時間も根気も必要ですが、評価されづらく属人化しやすい業務でもあります。
⑤ 製造業特有の複雑な技術環境
- 工場のIoT機器
- 生産系システムとの連携
- 物流系システムとの連携
- 雇用形態・勤務時間の複雑さ
- 海外拠点との通信や時差
- セキュリティ要件の厳格さ など
こうした“製造業ならでは”のIT対応が必要となる場面では、一定の専門知識や現場感覚が求められ、結果として担当者がますます限られた人材に偏りがちです。
📌こうして日々の問い合わせ対応が積み重なり、ヘルプデスク業務を担う社内のIT担当者が“本来やるべき改善業務”にまったく手をつけられないという悪循環に陥っているのが現状です。
このまま放置すると…生産性も人も壊れる
ヘルプデスクの負担は、見えにくいだけで確実に会社の“生命線”を圧迫しています。放置すれば大きなリスクに直結します。
対応ミスが重大な業務停止につながる
トラブル対応が遅れたことで、生産ラインが停止、出荷が遅延した――。
そんな事態は、実際に中小製造業で起こり得るリスクです。
「たかが問い合わせ」ではなく、現場の安定稼働に不可欠な役割であることを経営層が正しく認識する必要があります。
担当者の離脱が“即・業務停止”になる可能性も
属人化が進んだヘルプデスク業務では、たった一人がいなくなるだけで問い合わせ対応がまったくできなくなる、というケースも少なくありません。
しかも、業務は感謝されにくく、現場からのクレーム対応が多く、残業や休日対応も発生しやすい――。
結果として「もう無理です」と離職するリスクが常に隣り合わせです。
経営層が現状を把握しづらい“見えない負荷”
ヘルプデスク業務は、成果が数字に表れにくいです。
そのため、何件対応しているのか、どれだけ時間がかかっているのかが上層部に伝わりづらく、改善提案も後回しになりがちです。
気づけば、社内の“誰にも見えていなかった地盤沈下”が起きていたというケースも。
DX推進どころか、現状維持すら危うくなる
本来は業務改善やIT活用を進めていくはずの社内体制が、「問い合わせ対応だけで毎日終わる」状況では、何も変えられない、変わらない会社になってしまいます。
📌ヘルプデスク業務を軽視・放置することは、会社の足元を崩す行為です。
今こそ、現場の“声にならない悲鳴”に目を向けるタイミングです。

今すぐ始めたい!
ヘルプデスク業務を軽くする5つの対策
「ヘルプデスク業務が大変なのはわかっているけど、具体的に何から始めればいいかわからない…」
そんな企業のために、すぐ取り組める5つの対策をご紹介します。
① よくある質問を“見える化”する
:FAQ・マニュアル・チャットボット
毎日のように寄せられる「プリンタが使えない」「ログインできない」「メールが送れない」などの基本的な問い合わせ。
これは社内FAQやマニュアルの整備で、確実に負担を減らせます。
さらに、TeamsやSlackなどの社内チャットツールと連携できるチャットボットやAIを活用すれば、24時間いつでも自動で回答が可能に。
「担当者に聞くより、調べた方が早い」状態をつくることで、問い合わせ自体の数を減らすことができます。
② 問い合わせ対応の“仕組み化”
:誰が・どこまで・どう動くかを明確に
属人化の原因のひとつは、対応範囲やルールが曖昧なことです。
「誰がどの内容を担当するのか」
「緊急度の判断基準は何か」
「対応できないときのエスカレーション先は?」
など、簡単なフロー図やチェックリストを用意するだけで、対応が分散され、精神的な負担も軽くなります。
現場でよく使われる「現物・現場・現実(3現主義)」を応用して、“現場で誰でも判断しやすい仕組み”を持つことがカギです。
③ 外部パートナーの力を借りる
:部分的なアウトソースの活用
「全部自社で対応するのは無理がある」
そんなときは、社内の仕組みづくりや初期設定だけでも外部に頼るという方法があります。
- FAQの設計と導入支援
- チャットボットやAI導入とマニュアル作成の伴走支援
- 一部業務(パスワードリセット等)の外注
- ツール導入時の社内トレーニング など
部分的にアウトソースすることで、社内のIT担当者が“コア業務”に集中できる体制をつくることができます。
④ ITリテラシー向上
:社員全体の“自立”を促す
問い合わせが多い背景には、使う側の知識不足や不安感もあります。
そこで、社内向けにちょっとした「ITのワンポイント講座」を実施するだけでも効果があります。
たとえば、
- 「メールトラブルのよくある原因と対処法」
- 「Teamsの活用Tips」
- 「ファイル保存のルールと整理術」
など、身近なテーマを1回10分程度で共有するだけでも、“聞く前に調べてみよう”という意識が育ちます。
⑤ 情報を集約できるツールを導入する
ヘルプデスク業務が“属人的”になっている原因のひとつは、履歴が残らないことです。
TeamsのチャンネルやGoogleフォームなどを使い、問い合わせの記録・蓄積・分析ができる環境を整えることで、業務改善のヒントも得られます。
📌「少しだけ変える」から始めて、「仕組みをつくる」へ。
この積み重ねが、担当者の負担軽減だけでなく、組織としての対応力向上につながります。

5. 負担軽減の一歩に:「ITおまかせアシスタント」という選択肢
「改善したいけど、自分たちだけでは難しい」
そんな企業にとって、“一緒に考え、実行してくれる外部の伴走者”は心強い存在です。
現場を理解するパートナーとして
「ITおまかせアシスタント」は、中小製造業のリアルな現場を熟知した支援サービスです。
単なる外注やシステム導入ではなく、日々のヘルプデスク業務や社内フローの改善まで、泥臭く伴走します。
例えば、
- よくある質問を整理してFAQやマニュアルを作成
- 社内の問い合わせ内容を分析し、フローを見直し
- ツール導入時の初期設定や定着支援
- リテラシー向上のための勉強会や資料提供 など
「丸投げ」ではなく「一緒につくる」が基本方針
「うちには専任のヘルプデスクはいない」
「担当者が一人で悩んでいる」
「改善したいけど時間も余裕もない」
そんな企業にこそ、“全部を任せる”のではなく、“一緒に解決していく”支援スタイルが合います。
「業務が回る状態」を一緒につくり、「改善し続けられる仕組み」を社内に残すことを目指しています。
📌「ちょっと話を聞いてみる」から始めてみるのも、十分な第一歩です。
ヘルプデスク業務を担う社内のIT担当者の負担を“構造的に”軽くするために、無理なく伴走してくれる外部パートナーの活用を、ぜひ選択肢に入れてみてください。
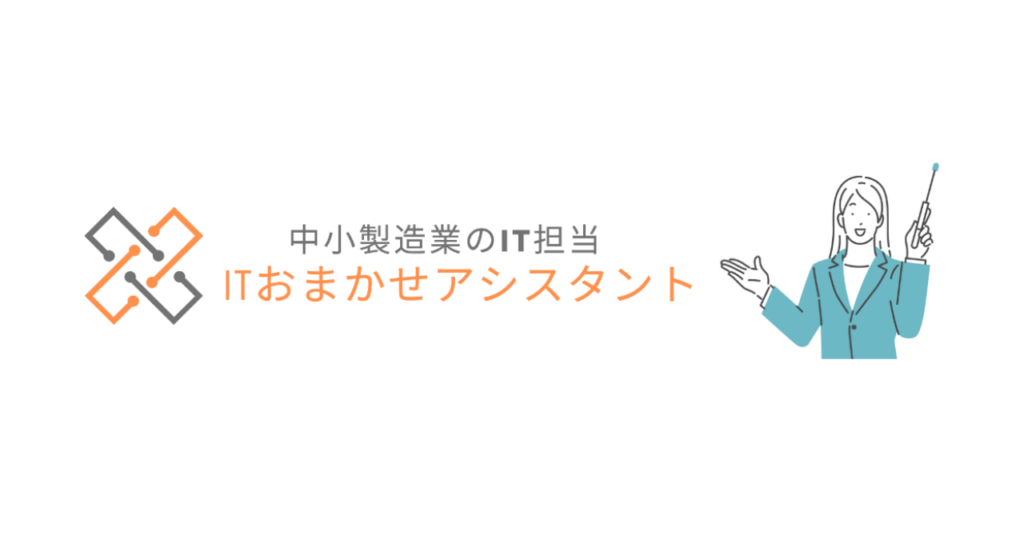
まとめ
:現場もIT担当も救う“仕組み化”の第一歩を
ヘルプデスク業務の効率化は、単に現場の便利さの話ではありません。
“業務を止めない会社”をつくるための、経営戦略の一部です。
ヘルプデスク業務を担う社内のIT担当者は、会社の“問題解決装置”とも言える存在。
しかしその業務は、成果が数字になりにくく、日報やKPIにも出にくいため、その重要性が見落とされがちです。
経営層がそこに気づき、改善に動き出すことで、
- 社員が安心して働ける職場
- トラブルに強い組織
- 働きやすく定着しやすいチーム
が、少しずつ、確実に形になっていきます。
今回ご紹介したような改善策は、多くが今日からでも始められる現実的な取り組みです。
- FAQを整理して問い合わせを減らす
- 社内ルールを明文化する
- 外部支援をうまく活用する
- ITに不慣れな社員を少しずつサポートする
こうした小さな変化の積み重ねが、現場の混乱を防ぎ、人材の離職を防ぎ、会社全体のパフォーマンスを底上げします。
📌「困っているのは現場だけじゃない。ヘルプデスク業務を担う社内のIT担当者も限界だ」
そう気づいた経営者が、今動くことで、“業務が止まらない会社”への第一歩が踏み出せます。
ぜひこのタイミングで、“一人で抱え込まない仕組み”づくりに踏み出してみてください。
「ITおまかせアシスタント」では、貴社の状況に合わせて、無理のないスタートをご提案いたします。
ちょっとした不安、現状の整理、料金のことまで、どんなことでもお気軽にお尋ねください。