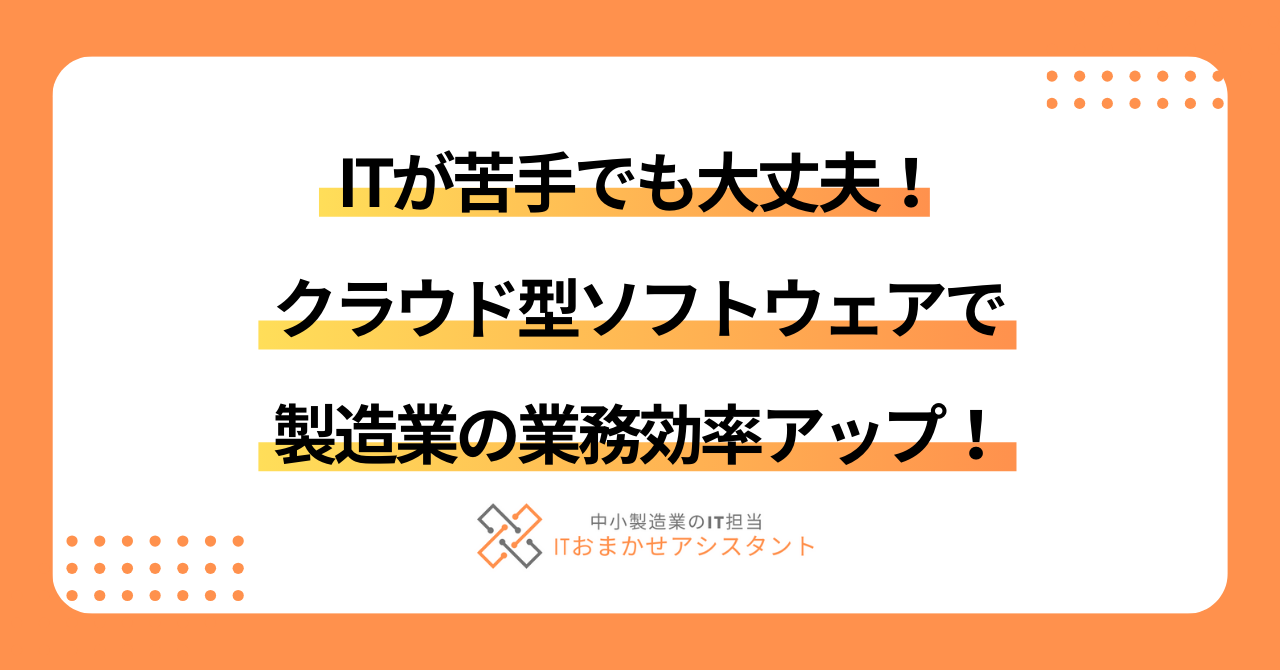「最近よく聞くクラウドやSaaS。でも、自社には関係ないのでは?」と感じたことはありませんか?
製造業でもIT活用が進む中、クラウド型ソフトウェア(SaaS)を導入する企業が増えています。しかし、「業務に合わないのでは?」「導入が難しそう」と不安を感じる企業も多いのが現状です。
クラウド型ソフトウェア(SaaS)とは、インターネットを通じて利用できるソフトウェアのことです。従来のようにパソコンにインストールしたり、自社サーバーを管理する必要がなく、インターネット環境さえあればどこからでも利用できるのが特徴です。
中小製造業でも、勤怠管理や会計、生産管理、在庫管理など、さまざまな業務を効率化するためにSaaSの活用が進んでいます。特に、IT担当者が不足している企業にとっては、大きなメリットがあります。
本記事では、なぜ今、SaaSが必要なのか? どのように活用できるのか? について、具体的な事例とともに解説していきます。「ITは苦手…」という方でも、無理なく導入できる方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
なぜ、中小製造業でSaaSなのか?
製造業の現場では、業務のデジタル化が急速に進んでいます。特に中小製造業にとって、限られた人員や資源の中でいかにIT化と業務効率化を進め、競争力を維持するかが重要な課題となっています。その解決策の一つとして、クラウド型ソフトウェア(SaaS)の導入が効果的と考えられています。では、なぜIT化が必要で、SaaSが有効なのでしょうか?その背景を見ていきます。
1. 人手不足の深刻化
「現場が回らない…」そんな声が、各地の中小製造業から聞かれるようになっています。
- 若手の採用が難しく、熟練工の引退が進んでいる
- 限られた人数でより多くの業務をこなす必要がある
- 事務作業の負担が増え、現場の業務に集中できない
少子高齢化の影響もあり、今後ますます人手不足が進むことが予想されます。今でも「人を増やして対応する」ことが難しいため、業務の効率化が避けられない課題になっています。
2. 業務の効率化が急務
中小製造業の多くでは、いまだに紙の伝票やExcelで業務を管理しているケースが見られます。
- 手作業によるミスが発生しやすい(例:受発注ミス、記録の抜け漏れなど)
- データの二重入力が多く、作業時間がかかる(例:伝票の手書き → Excel入力 → システム転記 など)
こうした作業の非効率さは、企業の成長を妨げる要因となります。ミスを防ぎ、正確でスピーディーな業務運営を実現するためには、従来の手作業管理からの脱却が求められています。
3. 競争力を維持するためのデジタル化
取引先や競合他社の多くがすでにITツールを導入し、デジタル化を進めています。
取引先から「デジタル対応」を求められる場面が増えている
例:「請求書をPDFで送ってほしい」「受発注データをオンラインで管理したい」など
IT化が進んでいない企業は、業務のスピードや精度で競争に遅れをとる可能性がある
業務のデジタル化を進めることで、取引のスピードを向上させるだけでなく、新しいビジネスチャンスにもつながります。従来の手法にこだわりすぎることで、将来的な取引機会を失うリスクもあるため、競争力を維持するためのデジタル対応は不可欠です。
4. SaaSはサーバーや開発・メンテ不要で導入しやすい
これまで業務システムを導入するには、自社でサーバーを構築し、ソフトウェアを制作し、インストールする必要がありました。しかし、SaaSはサーバーやソフトウェア開発とアップデートが不要で、インターネット環境さえあれば利用できます。
- 初期投資を抑えられる(サーバーや専用機器、開発が不要)
- IT担当者がいなくても運用できる(システム管理の大半をSaaS提供会社が行う)
- 常に最新の状態で使える(自動アップデート機能)
特に、中小製造業ではIT専門の人材を確保することが難しいため、「難しい管理なしで、手軽に導入できる」という点は極めて大きなメリットです。
中小製造業において、SaaSの導入は単なる業務効率化の手段ではなく、人手不足への対応、競争力の維持、コスト削減といった経営課題を解決するための有力な選択肢です。
クラウド型ソフトウェア(SaaS)とは?
中小製造業におけるデジタル化の必要性が高まる中、その手段として「クラウド型ソフトウェア(SaaS)」の活用が注目されています。では、SaaSとは具体的にどのようなものなのでしょうか?
1. SaaSの基本
SaaS(Software as a Service)とは、インターネットを通じて利用できるソフトウェアサービスのことです。従来のようにパソコンにインストールする必要がなく、Webブラウザや専用アプリを通じて手軽に利用できるのが特徴です。
これにより、業務のデジタル化を進めやすくなり、多くの企業で導入が進んでいます。
2. SaaSで使える業務管理ソフトの例
SaaSはさまざまな業務領域で利用されており、中小製造業でも導入が進んでいます。以下に、よく使われているSaaSツールの例を紹介します。
勤怠管理
- ジョブカン(シンプルな操作で出勤・退勤管理をクラウド化)
- Touch On Time(打刻データの自動集計機能が充実)
会計管理
- freee(中小企業向けのクラウド会計システム)
- マネーフォワードクラウド(会計をはじめバックオフィス業務を効率化)
生産管理
- ATOMS QUBE(中小製造業向けの生産管理システム)
- GROW工程管理(生産工程の可視化に特化)
在庫管理
タスク・プロジェクト管理
電子契約
コミュニケーション
- Google Workspace(Gmail、カレンダー、ドライブなどの統合ツール)
- Microsoft Teams(チャット、ビデオ会議、ファイル共有を一元化)
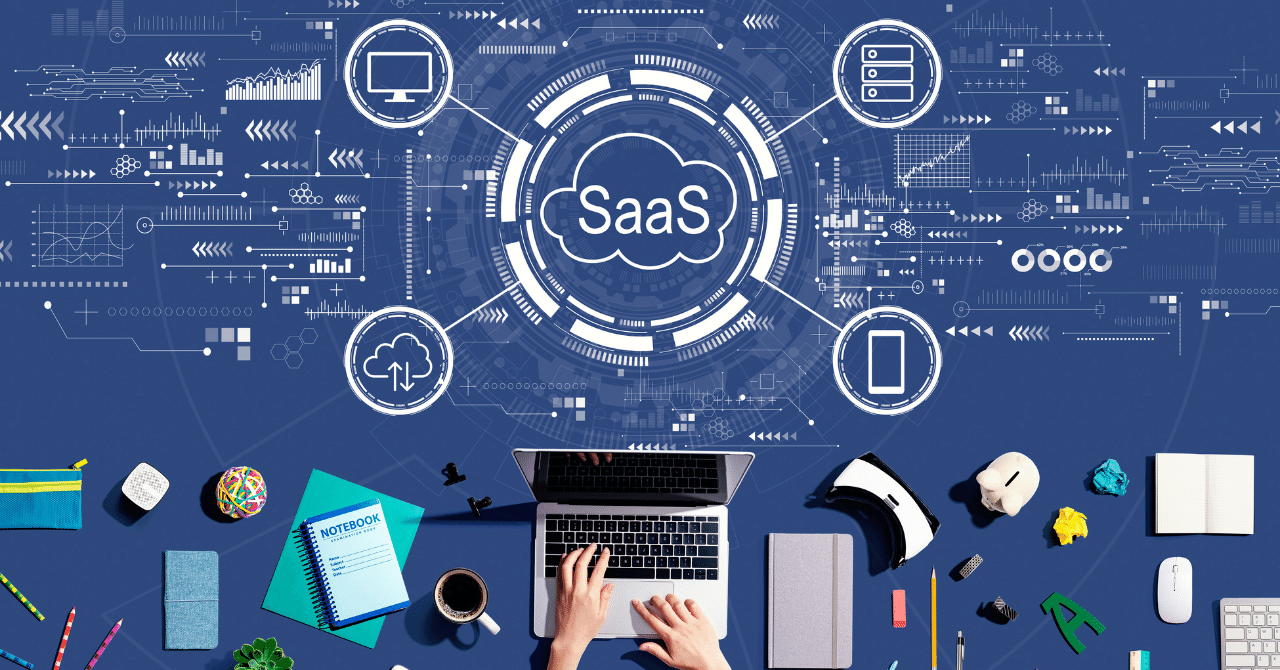
SaaSのメリット・デメリット
SaaSは、業務の効率化やコスト削減に役立つ一方で、いくつかの注意点もあります。ここでは、SaaSを導入することで得られるメリットと、導入時に考慮すべきデメリット、その対策について解説します。
1. SaaSのメリット
導入が簡単で、初期費用を抑えられる
SaaSは、インターネット経由で提供されるため、インストールや専用機器の購入が不要です。これにより、従来のオンプレミス型システムと比較して、初期導入コストを大幅に抑えられるのが特徴です。
- サーバーの構築が不要 → IT人材が不足している中小企業でも導入しやすい
- 自動アップデート対応 → メンテナンスの手間がかからず、常に最新の機能を利用可能
- サブスクリプション型の料金体系 → 必要な機能だけを選択でき、柔軟なコスト管理が可能
特に、中小企業では、IT専門の担当者を置くのが難しいケースが多いため、管理不要な点も大きな利点です。
どこからでも業務ができる
SaaSは、インターネットがあれば、どこからでもアクセスできるため、出張先や自宅など、オフィス外からも業務を進めることが可能です。
- 工場・支店・本社間でのデータ共有がスムーズ → 業務のリアルタイム化が可能
- リモートワークに対応しやすい → 柔軟な働き方を実現
例えば、クラウド型の在庫管理ソフトを導入すれば、スマートフォンやタブレットからリアルタイムで在庫状況を確認できるため、現場の迅速な意思決定にもつながります。
作業のミス・漏れを防げる
紙の伝票やExcel管理では、入力ミスや情報の抜け漏れが発生しやすいですが、SaaSを活用することで業務の一元管理が可能になります。
- 受発注・在庫・生産管理を一つのシステムで統合できる
- 二重入力の手間を削減し、人的ミスを防ぐ
- データがリアルタイムで更新されるため、最新情報を確認しやすい
例えば、販売管理SaaSを導入すれば、受注データをそのまま請求書作成に連携でき、転記ミスを防ぐことが可能です。
セキュリティを強化することができる
「クラウドは安全なの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、適切な管理を行えば、オンプレミスよりも強固なセキュリティを実現できます。
- データはクラウド上に保存され、災害・機器故障による消失リスクが低い
- クラウド事業者が最新のセキュリティ対策を実施(データ暗号化・多重バックアップ)
- アクセス管理や権限設定が可能 → 不正アクセスを防ぐ
例えば、定期的なセキュリティアップデートが自動で適用されるため、自社での対策よりも安全性が高い場合があります。
2. SaaSのデメリットとその対策
SaaSには多くの利点がありますが、導入に際してはいくつかのデメリットも考慮する必要があります。
インターネット環境に依存する
SaaSはクラウド上で動作するため、インターネットが不安定だと業務に支障が出る可能性があります。特に、通信障害やサーバーダウンが発生すると、一時的にシステムを利用できなくなるリスクがあります。
🎯対策
- バックアップ回線を用意し、回線障害時のリスクを低減する
- オフラインモード対応のSaaSを選ぶ(例:Googleドライブのオフライン編集機能など)
自社業務の対応が難しい場合がある
SaaSはパッケージ型のサービスであるため、自社の業務フローに完全にフィットしない場合があります。特に、オンプレミス型のシステムと比べると、細かい仕様変更が難しいケースもあります。
🎯対策
- 業務を先にシンプルにしてからSaaSを導入する
- API連携(異なるソフト同士をつなぎ、自動でデータをやり取りする仕組み)が可能なSaaSを選び、他のシステムと組み合わせて活用する
- 業界向けのSaaSを選定し、業務に合った機能を備えたものを導入する
他のシステムへの乗り換えが難しい
SaaSを導入した後、「別のSaaSの方がコストが低い」「機能が自社の業務により適している」と感じても、簡単には乗り換えられません。特に、現場の担当者がすでに使い慣れている場合、変更に対する抵抗が生じることもあります。
🎯対策
- 重要なSaaSの選定は、事業の成長を踏まえた中長期的な視点で行う
- 乗り換えの可能性が出てきたら、早めにデータ移行について検討する
セキュリティリスクがゼロではない
SaaSはクラウド上にデータを保存するため、情報漏洩のリスクが完全になくなるわけではありません。また、アクセス制御が不十分な場合、不正アクセスの可能性もあります。
🎯対策
- 2段階認証を導入し、アクセス権限を適切に管理する
- 従業員向けのセキュリティ教育を定期的に実施し、意識を高める
取引先がSaaSに対応していない場合がある
SaaSを導入しても、取引先が紙ベースやExcelで業務を行っている場合、データのやり取りがスムーズに進まないことがあります。
🎯対策
- ExcelやPDF形式での出力が可能なSaaSを選び、取引先との連携をスムーズにする
- 段階的に取引先にもデジタル化を提案し、共通のシステムを導入する可能性を探る
SaaSは導入しやすく、業務の効率化に大きく貢献する一方で、インターネット環境の依存やカスタマイズの制約といったデメリットもあります。しかし、適切な対策を講じることで、デメリットを最小限に抑えながら効果的に活用することが可能です。

SaaSの導入ステップ
SaaSの導入は、小規模なテスト運用から始め、段階的に展開することが成功のカギです。多くのSaaSは無料プランやトライアルを提供しているため、活用しながらスムーズな導入を進めましょう。
1. ニーズの明確化
まず、どの業務を改善したいのかを明確にします。現場の課題を洗い出し、必要な機能を整理しましょう。
また、中長期的に見て少し先のニーズも考えましょう。
例:
- 経理部門:「請求書処理を効率化したい → ペーパーレス化できるSaaSを検討」
- 営業チーム:「顧客情報の管理を統一したい → CRMを導入」
- 人事部門:「給与計算のミスをなくしたい → 自動計算機能付きのSaaSを選定」
2. サービスの選定
市場にあるSaaSの中から、無料プランやトライアルを提供しているサービスを実際に試すことで、最適なものを見極めます。
✔ 機能(課題を解決できるか)
✔ コスト(料金プランが適正か)
✔ 操作性(現場で簡単に使えるか)
✔ サポート体制(問い合わせ対応が充実しているか)
✔ セキュリティ(データ管理が安全か)
この際、導入負担が少なく、小規模で運用開始しやすいSaaSを選ぶことがポイントです。
3. 無料プラン・トライアルでのテスト運用
いきなり全社導入するのではなく、無料プランやトライアルを活用し、小規模な範囲で試験運用を行いましょう。
例:
- 営業チームの3人でCRMを1ヶ月テスト
- 経理担当者が会計ソフトの無料プランを試し、業務フローとの適合性を確認
この段階で「操作が難しい」「業務フローに合わない」などの問題があれば、導入前に別のサービスを検討できます。
4. 社内展開・導入
テスト運用で問題がなければ、段階的に社内へ展開します。
- 運用ルールの策定(権限設定、入力ルールの統一)
- 研修・マニュアルの作成(動画やPDFで基本操作を説明)
例:勤怠管理SaaSの導入
- 人事向け:36協定のチェックや給与システムへの連携の方法を資料化
- 管理者向け:シフト作成や承認フローの設定方法を説明
- 従業員向け:打刻や休暇申請のやり方を説明
全社展開する際も、一度に全員に適用せず、段階的に展開することで混乱を防ぎます。
5. 効果測定と最適化
導入後は、KPIを設定し、期待した効果が出ているか定期的に評価しましょう。
✔ 時間短縮:「請求書処理が○%短縮」
✔ コスト削減:「年間○万円の経費削減」
✔ 業務効率化:「給与計算の作業時間が1日短縮」
例:SaaS導入後の見直し
- 1ヶ月後:「経費精算の負担が軽減、順調」
- 3ヶ月後:「一部の従業員が使いこなせない → 追加研修実施」
- 6ヶ月後:「さらに活用できる機能を設定」
運用しながら継続的に改善し、より業務にフィットさせることが重要です。
SaaSの導入は、無料プランやトライアルを活用した小規模運用→段階的な本格導入→定期的な見直しが成功のポイントです。この手順を踏むことで、スムーズにSaaSを定着させ、業務の効率化を実現できます。
よくある不安とその解決策
SaaSの導入を検討する際、多くの企業が不安に感じるポイントがあります。しかし、実際にはこれらの課題は適切なツール選びやサポート体制を活用することで解決可能です。ここでは、特によくある3つの不安とその解決策を紹介します。
1. ITが苦手な社員でも使える?
SaaSは「ITに詳しくないと使えないのでは?」と心配されることがあります。しかし、多くのSaaSは直感的に操作できるよう設計されており、特別なスキルがなくても問題なく使えます。
操作はシンプルで、スマホやタブレットでも利用可能
例:「ジョブカン」は、ボタンを押すだけで出退勤の記録ができる
トレーニングやサポート体制が充実している
例:「freee」では、動画マニュアルやチャットサポートを提供
また、導入時に簡単な研修を行うことで、社内でのスムーズな運用が可能になります。
2. 導入コストが心配
「初期費用が高いのでは?」という懸念もありますが、SaaSは月額制(サブスクリプション型)のため、大きな初期投資は不要です。
利用した分だけ支払う料金体系が一般的
必要な機能に絞ってコストを最適化できる
補助金を活用すれば、実質負担額がかなり減らして導入可能
IT導入補助金や自治体の支援制度を活用することで、導入費用を抑えられる
まずは無料プランやトライアルを試し、費用対効果を確認した上で導入するのがベストです。
3. 取引先とのデータ連携は大丈夫?
「取引先がクラウドに対応していないと、データのやり取りが難しいのでは?」という不安もありますが、多くのSaaSはExcelやPDF形式での出力に対応しているため、スムーズに連携可能です。
取引先のデジタル化が進んでいなくても、SaaSのデータ出力機能を活用することで、従来の紙やExcelベースの運用とも併用できるため、スムーズな導入が可能です。
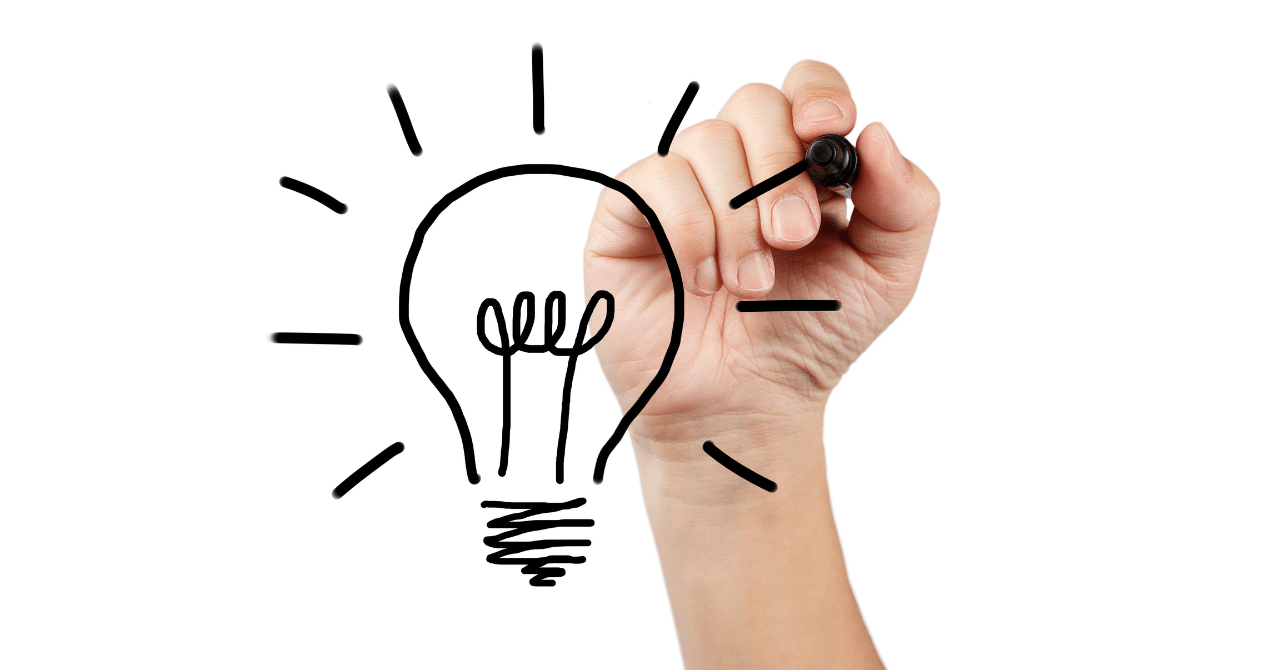
具体的な導入事例
SaaSを導入することで、実際にどのような成果が得られるのかをイメージすることは重要です。ここでは、勤怠管理と在庫管理の2つの事例を紹介します。
事例①:勤怠管理のSaaS導入で業務効率UP
📌 課題:タイムカードの手入力によるミスが多発
ある中小製造業では、従業員の勤務時間をタイムカードで管理し、毎月手作業で集計していました。しかし、記録のミスや計算間違いが頻発し、給与計算のたびに確認作業に多くの時間を取られている状態でした。
✅ 解決策:「Touch On Timez」を導入し、スマホで打刻
- 従業員がスマホやPCから打刻できるようにし、手入力を廃止
- 勤怠データがクラウド上に自動保存され、リアルタイムで管理可能に
- 給与計算ソフトとのデータ連携機能を活用し、作業の自動化を実現
📊 結果:毎月の集計時間が10時間→30分に短縮
- 手作業での入力が不要になり、計算ミスがゼロに
- 勤怠データが即時に反映され、リアルタイムでの管理が可能に
- 締め作業にかかる時間が大幅に削減され、管理部門の負担が軽減
事例②:在庫管理のSaaS化でミス削減
📌 課題:在庫管理がExcelベースで、データ更新が遅い
別の中小製造業では、在庫管理をExcelで行っていました。しかし、現場と事務所で情報が共有されておらず、更新のタイミングがズレることが頻発。結果として、在庫不足や過剰在庫の発生が問題となっていました。
✅ 解決策:「zaico」を導入し、リアルタイムで在庫情報を共有
- 倉庫の在庫状況をスマホやタブレットからリアルタイムで確認可能に
- 出荷・入荷の記録をクラウド上で一元管理し、情報の更新遅れを解消
- バーコードスキャン機能を活用し、入力作業の手間を削減
📊 結果:在庫ミスが削減され、業務の効率が向上
- リアルタイムで在庫状況を確認できるため、発注のタイミングが正確に
- 過剰在庫の削減に成功し、無駄なコストを削減
- 取引先からの在庫照会にもすぐに対応できるようになり、顧客満足度が向上
まとめ|今こそ、SaaSを活用しよう!
SaaSは、中小製造業の業務効率化を大きく前進させるツールです。勤怠管理や在庫管理、生産管理など、さまざまな業務をシンプルにし、現場の負担を軽減できます。手作業のミスを減らし、データをリアルタイムで共有することで、よりスムーズな業務運営が可能になります。
「導入が難しそう」「うまく使えるか不安」という声もありますが、多くのSaaSは直感的に操作でき、サポート体制も充実しています。まずは無料プランやトライアルを活用し、小さな範囲から始めることで、スムーズな導入が実現できます。
業務のデジタル化は、企業の成長に不可欠なステップです。SaaSを活用し、効率的な働き方を取り入れてみませんか?
ITに関してのお困りごとがあればご相談ください。