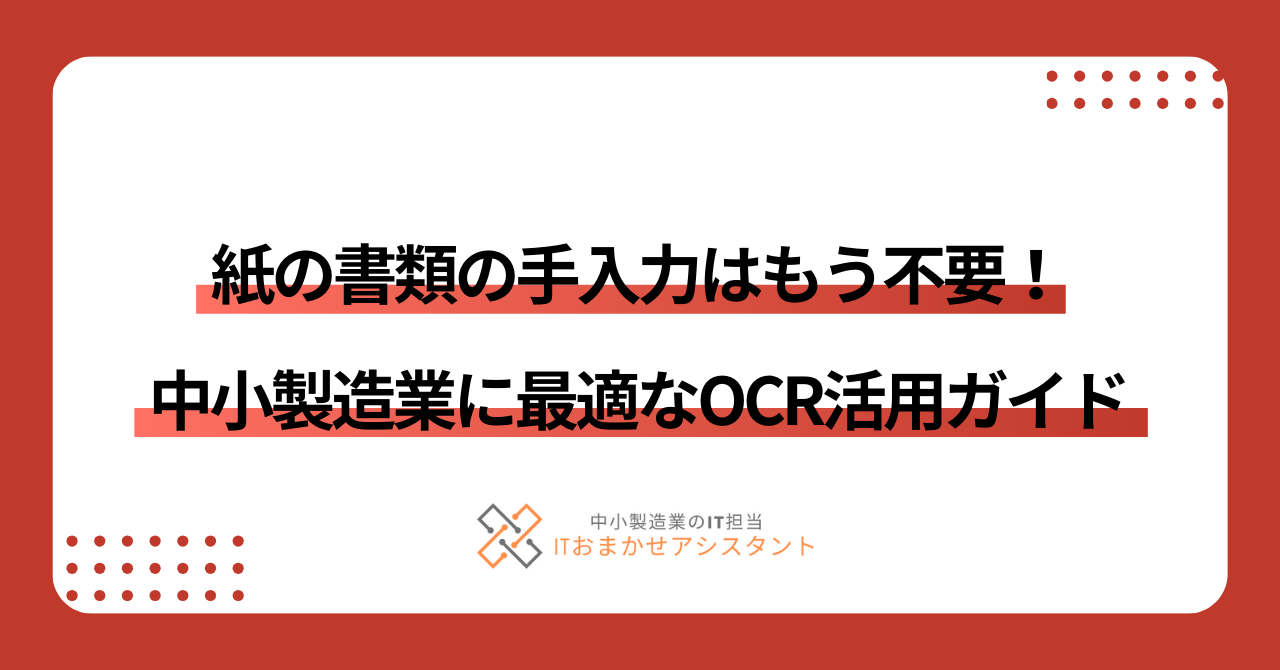目次
1. はじめに
中小製造業では、受発注書、納品書、請求書などの紙の書類が多く、手作業でのデータ入力に時間がかかることが課題です。手作業での転記ミスが発生し、業務負担が増してしまうケースも少なくありません。
そこで、業務効率化の鍵となるのが OCR(光学文字認識) です。
✅ OCRを導入すると、紙の情報をデジタル化し、手入力が不要に!
✅ 転記ミスがなくなり、業務の精度が向上!
さらに、OCRと RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) を組み合わせることで、データ処理まで自動化することも可能になります。
📌 OCR × RPAの活用例
- 注文書をOCRでデータ化し、そのままシステムへ自動入力
- 納品書の情報をOCRで読み取り、RPAが会計ソフトに自動登録
紙の書類を減らし、業務の無駄をなくしたいと考えているなら、OCRの導入を検討してみましょう。
2. OCRとは?
「OCRってよく聞くけど、実際にどんなもの?」
OCR(Optical Character Recognition:光学文字認識)は、紙の書類や画像データに含まれる文字を認識し、テキストデータとして変換する技術です。
これにより、手入力をせずに紙の書類をデジタル化できるため、業務の効率化に大きく貢献 します。
よく使われるOCRの種類
OCRには大きく分けて3つの言葉で説明されます。
📌活字OCR(Printed OCR)
- 印刷された活字を認識する技術。
- 請求書や納品書などの印刷文書に適している。
- 認識精度が高く、スムーズにデータ化可能。
📌手書きOCR(Handwriting OCR)
- 手書きの文字を認識する技術。
- 作業日報やメモなど、手書き書類のデジタル化に活用。
- 文字の癖によって認識精度が異なるため、場合によっては補助入力が必要。
📌AI OCR(Artificial Intelligence OCR)
- 機械学習を活用し、活字だけでなく手書き文字や非定型書類にも対応。
- フォーマットが一定でない書類(異なるレイアウトの請求書など)でも高精度で認識。
- 文字の補完や学習機能を備えており、使えば使うほど精度が向上。
OCRの得意・不得意な分野
OCRは非常に便利な技術ですが、得意な領域と不得意な領域があります。
✅ 得意な分野
- 活字で印刷された書類(請求書、納品書、発注書など)
- 定型フォーマットの文書
- 解像度の高いスキャンデータ
❌ 不得意な分野
- 崩れた手書き文字やクセの強い筆跡
- 解像度が低く、ぼやけたスキャン画像
- 表や図の中に埋め込まれた文字
OCRの活用には、スキャン時の画質やフォーマットの統一が重要になります。
中小製造業におけるOCRの活用シーン
中小製造業では、OCRをどのように活用できるのでしょうか?
📌 発注書のデータ化
- 顧客から送られてくる発注書をOCRで読み取り、自動で受注のシステムに登録。
- 紙の書類をデジタル化し、検索・管理を容易に。
📌 納品書・請求書の処理
- 納品書や請求書をOCRで読み取り、会計ソフトに自動入力。
- 手作業での転記をなくし、ミスを削減。
📌 作業日報の電子化
- 現場作業員が記入した手書きの日報をOCRでデジタルデータ化。
- 集計や分析が容易になり、管理の効率が向上。
OCRを活用することで、紙の書類が引き起こす「入力作業の負担」や「転記ミス」を大幅に減らすことができます。

3. なぜ中小製造業にOCRが向いているのか?
中小製造業は紙の書類が多いため、OCRを活用することで大きな効果が得られます。そしてOCRは導入しやすいです。
1. 紙の書類が多い業界だからこそ効果が大きい
発注書、納品書、請求書、作業日報など、中小製造業では紙の書類が日常的に発生します。手入力を続けると、作業時間がかかり、転記ミスも発生しやすいという課題があります。
OCRを導入すると、これらの書類をスキャンしてデジタル化し、入力作業の削減とミスの防止が可能になります。たとえば、発注書をOCRで読み取り、受発注のシステムに自動入力すれば、処理時間が短縮され、業務の精度が向上します。
2. IT人材が不足していても導入しやすい
中小製造業ではIT担当者がいない、または少人数でシステムを管理しているため、複雑なシステムの導入が難しいという課題があります。
しかし、最近のOCRツールはクラウド型が増えており、専門知識がなくても簡単に導入・運用が可能です。
📌 クラウド型OCRのメリット
- インストール不要で、すぐに利用開始できる
- メンテナンス不要で、常に最新の状態で利用できる
- サポートが充実しており、トラブル時も安心
請求書をOCRでデータ化し、会計ソフトに自動入力するなど、ITスキルがなくても業務の効率化を実現できます。
3. コストパフォーマンスが良い(特にクラウド型OCR)
以前のOCRシステムは高価でしたが、現在はクラウド型OCRが主流になり、手頃なコストで導入できるようになりました。
📌 クラウド型OCRのコストメリット
- 初期投資が不要(サーバー不要)
- 月額制で必要な分だけ利用できる
- スモールスタートが可能で、規模に応じた拡張ができる
例えば、手作業で請求書を処理するよりも年間数百時間の業務削減が可能になり、転記ミスの削減によるトラブル防止にもつながります。
4. DX(デジタル化)の第一歩として有効
OCRの導入は、業務のデジタル化(DX)の最初のステップとして効果的です。紙の書類をデジタル化することで、業務フローを大きく変更せずに効率化ができます。
📌 OCR導入がDX推進の第一歩になる理由
- 既存の業務を大きく変えずにデジタル化できる
- データを活用しやすくなり、後の自動化(RPA導入など)につなげられる
- 社内のデジタル化への抵抗感を減らせる
まずOCRで紙のデータ化を進め、その後、RPAなどの自動化ツールと組み合わせてさらなる効率化を目指すのがスムーズなDXの進め方です。
OCRを活用すれば、データ入力の手間を削減し、業務の効率化とミス削減を両立できます。

4. OCR導入のメリット
OCRを導入することで、手作業の負担を軽減し、業務効率を大幅に向上させることができます。ここでは、OCRの主なメリットを紹介します。
1. 入力作業の手間削減
中小製造業では、受発注書や請求書などの書類を手作業で入力するケースが多いですが、OCRを活用すれば、この作業を自動化できます。
🔸 OCR導入前の課題
- 手入力に時間がかかる
- 入力ミスが発生しやすい
- 処理が遅れ、業務のボトルネックになる
🔹 OCR導入後の効果
- スキャンするだけでデータを自動取り込み
- 作業時間が短縮され、担当者の負担が軽減
- 業務スピードが向上し、処理の遅延を防げる
例えば、請求書処理にOCRを導入した企業では、入力作業の時間が50%以上削減された事例もあります。
2. 転記ミスの削減
手入力による数字の誤りや記入ミスは、受発注ミスや請求ミスにつながることがあります。OCRを活用すれば、転記ミスを大幅に削減できます。
🔸 OCR導入前の課題
- 数字や品番を間違えることがある
- 受注ミス・請求ミスが発生し、修正作業が増える
- 確認作業に時間がかかる
🔹 OCR導入後の効果
- 書類の情報をそのままデータ化し、転記ミスを防止
- 入力ミスが減り、修正作業が不要に
- 業務の正確性が向上し、信頼性が高まる
請求書処理のミスがゼロになり、確認作業の時間が1/3に短縮された企業もあります。
3. 書類の検索・管理がラクになる
紙の書類はファイリングや保管に手間がかかるだけでなく、必要なときにすぐに見つけられないこともあります。OCRを活用し書類をデジタル化することで、検索や管理が簡単になります。
🔸 OCR導入前の課題
- 書類が大量にあり、管理が煩雑
- 必要な書類を探すのに時間がかかる
- 書類の紛失リスクがある
🔹 OCR導入後の効果
- キーワード検索で必要な書類をすぐに見つけられる
- クラウド管理で、どこからでもアクセス可能
- 紙の保管スペースを削減し、オフィスの整理が進む
納品書をデータ化した企業では、書類検索にかかる時間が90%削減されたという事例もあります。
4. ペーパーレス化の第一歩
ペーパーレス化を進めたい企業にとって、OCRの導入は紙の書類をデジタル化する第一歩になります。
🔸 OCR導入前の課題
- 紙の書類が多く、スペースを圧迫
- 印刷や保管にコストがかかる
- 書類の処理が煩雑で、業務が停滞しやすい
🔹 OCR導入後の効果
- 書類の電子化で、ペーパーレス化を推進
- 印刷・保管コストの削減
- デジタルデータを活用し、業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)につなげる
例えば、受発注書のOCR導入により、年間100万円以上の印刷・保管コスト削減に成功した企業もあります。
OCRを活用することで、業務の負担を軽減し、より生産的な業務に集中できる環境を整えられます。

5. OCR導入のステップと成功のポイント
OCRを導入する際は、計画的に進めることが成功のカギです。ただ単に導入するだけでは効果を最大限に発揮できません。適切なステップを踏みながら進めることで、スムーズに業務のデジタル化を実現できます。
ここでは、OCR導入の流れと成功のポイントについて詳しく解説します。
1. 業務の棚卸しを行う(どの業務でOCRを活用するべきか?)
まずは、OCRをどの業務に導入するのが最も効果的かを見極めることが重要です。
企業によって、紙の書類の多い業務や、デジタル化のメリットが大きい業務は異なります。そこで、以下のような視点で業務の棚卸しを行いましょう。
✅ どんな書類が手作業で処理されているか?
✅ どの業務で入力作業に時間がかかっているか?
✅ ミスが発生しやすい業務はどこか?
📌 具体例:OCR導入に向いている業務
- 受発注処理:発注書や注文書の入力作業を削減
- 請求書処理:請求書の情報を自動でデータ化
- 納品書管理:納品書の記録をデジタル化し、検索しやすくする
- 作業日報の管理:手書きの日報をデータ化し、分析しやすくする
例えば、「請求書の手入力に時間がかかっている」という課題があれば、OCRを導入することでデータ入力の時間短縮や転記ミスの削減が期待できます。
2. OCRの種類を選ぶ(手書きOCRの精度、AI OCRの必要性を確認)
OCRには活字OCR・手書きOCR・AI OCRの3種類があります。導入する業務に応じて、適切なOCRを選びましょう。
📌 OCRの種類と特徴
| OCRの種類 | 特徴 | 向いている業務 |
| 活字OCR | 印刷された活字を高精度で認識 | 納品書・請求書・発注書 |
| 手書きOCR | 手書き文字を認識(精度はやや低め) | 作業日報・点検記録 |
| AI OCR | AIが学習しながら精度を向上 | フォーマットが異なる書類 |
例えば、フォーマットが一定の請求書なら活字OCR、手書きの日報を処理するなら手書きOCRやAI OCRが適しています。また、異なるレイアウトの書類を扱う場合は、AI OCRを活用することで認識精度を向上させることができます。
✅ 選定ポイント
- どのタイプの書類を処理するか?
- 精度の高さが求められるか?
- コストに見合う効果が得られるか?
3. 小規模なテスト導入を実施する(まず1つの業務で試し、効果を検証)
いきなり全社導入するのではなく、まずは小規模な範囲でOCRを試してみるのが成功のポイントです。
📌 テスト導入の進め方
- 1つの業務を選ぶ(例:請求書の処理)
- OCRツールを試用(無料トライアルやデモを活用)
- 導入前後の比較を行う(作業時間・ミス発生率など)
- 課題を洗い出し、運用ルールを整備する
例えば、「OCRを導入したら請求書の処理時間が50%短縮できた」「転記ミスがゼロになった」など、具体的な成果が見えてから本格導入すると、スムーズに社内展開できます。
4. 本格導入し、他の業務にも展開(OCRと他のシステムとの連携を考慮)
テスト導入で効果が確認できたら、本格的にOCRを導入し、他の業務にも展開していきます。
📌 本格導入の流れ
- 導入範囲を拡大(他の書類・業務にも適用)
- OCRデータを他のシステムと連携(基幹システムやRPAとの連携)
- 運用ルールを確立し、社内に定着させる
例えば、請求書処理でOCRを活用した後、次に納品書・受発注処理にも拡大することで、業務全体の効率化が可能になります。
また、OCRでデータ化した情報を会計ソフトやERP(基幹システム)と連携すれば、さらなる業務の自動化が実現できます。
このように、段階的に導入を進めることで、リスクを抑えつつ、業務の効率化を実現できます。
6. 発展編:OCRだけでは不十分?RPAと組み合わせるメリット
OCRを導入すると、紙の書類をデジタル化できますが、その後のデータ入力や処理は手作業が必要になることが多く、業務の効率化が不十分に感じることがあります。そこで活用したいのが RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) です。
OCRとRPAを組み合わせることで、データ化からシステム入力までを自動化し、さらなる業務効率化を実現できます。
1. OCRの限界:データ化はできるが、その後の処理は手作業
OCRは紙の書類をデジタル化する便利なツールですが、データ化した後にシステムへ入力する作業は手動で行う必要があるため、以下のような課題が残ります。
🔸 OCRのみの場合の課題
- 受発注書のデータをシステムに手入力する必要がある
- OCRで読み取った請求書データを会計ソフトに転記する手間が発生
- 作業日報のデータを手動で整理し、集計する時間がかかる
こうした作業をRPAで自動化すれば、手作業を大幅に減らし、業務効率を最大化できます。
2. RPAとは?(パソコン上の繰り返し作業を自動化)
RPAは、パソコン上で行う定型作業を自動化するツールです。
📌 RPAの特徴
✅ Excelや会計ソフト、基幹システムの操作を自動化
✅ 毎日発生する定型作業をプログラムが代行
✅ ヒューマンエラーを防ぎ、業務スピードを向上
RPAは、OCRがデジタル化したデータを自動で処理するため、入力作業が不要になります。
3. OCR×RPAの活用例
OCRとRPAを組み合わせることで、以下の業務を自動化できます。
① 受発注業務の自動化
OCRのみ:発注書をOCRで読み取るが、システム入力は手作業
OCR×RPA:OCRがデータ化し、RPAがシステムへ自動入力し、確認メールを送信
💡 効果:受注処理の時間を短縮し、業務負担を軽減!
② 請求書処理の効率化
OCRのみ:請求書をOCRでデジタル化するが、会計ソフトへの登録は手作業
OCR×RPA:OCRがデータを抽出し、RPAが会計ソフトに自動入力
💡 効果:転記ミスを防ぎ、請求処理をスムーズに!
③ 作業日報の自動集計
OCRのみ:手書き日報をOCRでデータ化するが、集計は手作業
OCR×RPA:OCRがデータを取得し、RPAが自動集計・レポート作成
💡 効果:作業進捗の把握が容易になり、管理工数を削減!
4. OCR導入後にRPAを検討するのがおすすめ!
いきなりOCRとRPAを同時に導入するのは大変なので、まずはOCRで入力作業を減らし、次のステップでRPAを検討するのがおすすめです。
📌 導入の流れ
1️⃣ OCRを導入し、手入力の負担を減らす
2️⃣ データの整理・活用が進んだら、RPAを試験導入する
3️⃣ OCR×RPAを組み合わせ、業務の完全自動化を目指す
OCRは書類のデジタル化に役立ちますが、その後の処理を手作業で行うと業務効率が十分に向上しません。そこでRPAを組み合わせることで、受発注処理や請求書処理などの業務を完全に自動化できます。
OCR導入後に「まだ作業負担が大きい…」と感じたら、RPAの活用も視野に入れると、さらなる業務改善が期待できます。
7. OCR導入の成功事例
OCRを導入したことで、実際に業務がどのように改善されたのか、具体的な事例を紹介します。
A社(製造業):受注処理の半自動化に成功!
🔸 課題:注文書の手入力作業に時間がかかり、転記ミスが発生
A社では、毎日数十件の注文書を手作業で入力しており、以下のような問題が発生していました。
✅ 受注データを基幹システムに入力するのに1日3時間以上かかる
✅ 手作業による入力ミスで、出荷ミスが発生
✅ 繁忙期になると注文処理が追いつかず、納期が遅れることがあった
🔹 OCR導入後の変化
A社では、注文書をOCRでスキャンし、データを基幹システムに自動入力する仕組みを導入しました。その結果、以下の改善が見られました。
✅ 入力作業が自動化され、1日3時間かかっていた作業が30分に短縮!
✅ 転記ミスがなくなり、受注ミスがゼロに!
✅ 繁忙期でもスムーズに処理できるようになり、納期遅れが解消!
💡 結果:OCR導入により、作業時間が大幅に削減され、受注処理の精度が向上!
B社(部品メーカー):請求書処理の効率化
🔸 課題:請求書処理に手間がかかり、月末の業務が逼迫していた
B社では、取引先から届く請求書を手入力で処理しており、以下のような問題が発生していました。
✅ 紙の請求書を1枚ずつ確認し、会計ソフトに入力するのに1件あたり5分かかる
✅ 月末に処理が集中し、経理担当者が長時間残業して対応
✅ 手入力のため、金額の入力ミスが発生し、修正作業が必要
🔹 OCR×RPA導入後の変化
B社では、請求書をOCRでスキャンし、データをRPAが自動で会計ソフトに入力する仕組みを導入しました。その結果、以下のような改善が見られました。
✅ 1件あたりの処理時間が5分 → 30秒に短縮!
✅ 月末の業務負担が大幅に減り、残業時間が50%削減!
✅ 請求書の入力ミスがなくなり、確認・修正作業が不要に!
💡 結果:OCRとRPAの組み合わせで、経理業務の負担が大幅に軽減!
OCRを活用することで、日々の業務をスムーズにし、生産性の向上につながります。次章では、OCR導入のポイントを総まとめしていきます。
8. まとめ
中小製造業では、紙の書類が多く、手入力作業が業務負担の原因になっています。OCR(光学文字認識)を導入すれば、データ入力の手間を削減し、転記ミスを防ぐことが可能です。
まずは、効果が大きい業務からOCRを試し、小規模な導入から始めるのがポイントです。さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)と組み合わせることで、データ入力や処理を自動化し、さらなる業務効率化が可能になります。OCRは、中小製造業の業務効率化に欠かせないツールです。手作業の負担を減らしたいなら、まずはOCRの導入から始めてみましょう!
ITに関してのお困りごとがあればご相談ください。