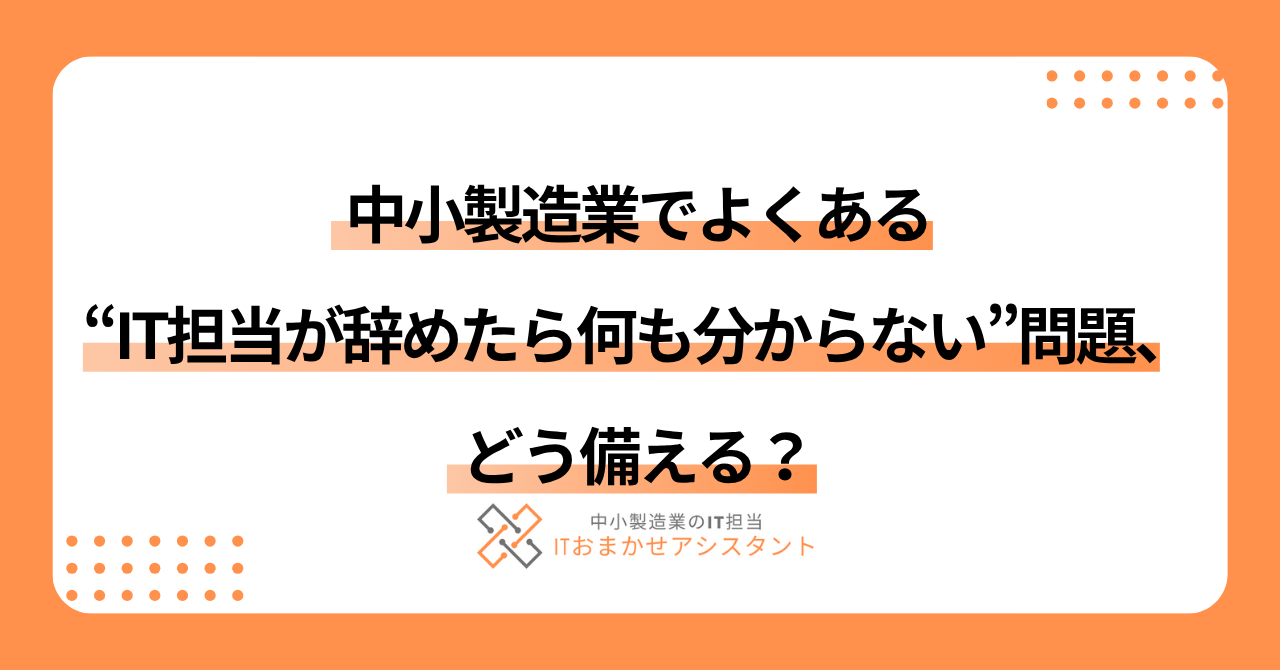目次
ある日突然、IT担当が退職すると…
「ちょっとITに詳しそうだったから任せてたんだけど、辞めるなんて聞いてないよ…」
そんな声を、経営者の方から聞くことがあります。
中小製造業では、いわゆる「ひとり情シス」「ITをちょっと知っている人任せ」的な状況が少なくありません。
社内でITに詳しい人が1人しかおらず、その人がパソコンの初期設定からネットワーク管理、さらにはトラブル対応まで、すべてを背負っているケースは非常に多いです。
そして、その“頼みの綱”に突然辞めたいと言われたとき、初めて気づくのです。
「この会社のITって、全部あの人が握ってたんだな」と。
社員の誰もシステムの仕組みを知らず、パスワードも不明。
「急ぎで直して」と頼まれても、どこがどうなっているか分からない。そんな事態に、社内は一気に混乱します。
これは珍しい話ではありません。特に、ITを専門に扱う人材が限られている企業では、「あの人に任せておけば安心」という思いが、いつの間にかリスクに変わってしまうことがあります。
本記事では、そんな“IT担当が辞めたら何も分からない”という状況をどう避けるか、どう備えるかについて、具体的な対策を交えて解説していきます。
よくあるパターンと“ありがちトラブル”
IT担当が辞めたあとに起きがちなトラブルは、実にさまざまです。
特に中小製造業では、少人数で業務を回していることが多いため、ひとつの情報が抜けるだけで、社内全体が大混乱に陥るケースもあります。
たとえば、
設定情報やExcelマクロをその人しか分からない
ファイルサーバーのアクセス設定や、製造現場で使っているExcelマクロ。
「Aさんしか知らない」「あれはAさんが全部作った」という状況はよくあります。
退職後に修正やトラブル対応が必要になっても、どこをどう触っていいか分からず、結局放置されてしまうことに…。
ITツールの契約管理が不明瞭
日報管理、顧客管理、勤怠管理など、クラウドサービスを複数使っている企業も多いと思います。
しかし、それぞれの契約内容・ID・支払情報などを管理していたのが本人だけだった場合、更新漏れやアクセス不能といったトラブルが続出します。
サーバーやネットワークの障害時、誰も対応できない
社内LANが繋がらない、メールが送れない、印刷ができない――そんなトラブルが発生しても、対応できる人がいないと、業務そのものが止まってしまいます。
普段何気なく使っていた「ITの基盤」が、いかにその人のスキルや記憶に頼っていたかを痛感する瞬間です。
こうした事態の多くは、「その人が辞めてから」初めて見えてきます。
つまり、すべてが属人化されていたことで、リスクが“潜在化”していたのです。
特に小規模な組織では、1人がいなくなるだけで社内の機能が一部停止してしまうほどの影響があります。
だからこそ、“辞められてから”ではなく、“辞める前に”備えておくことが重要なのです。
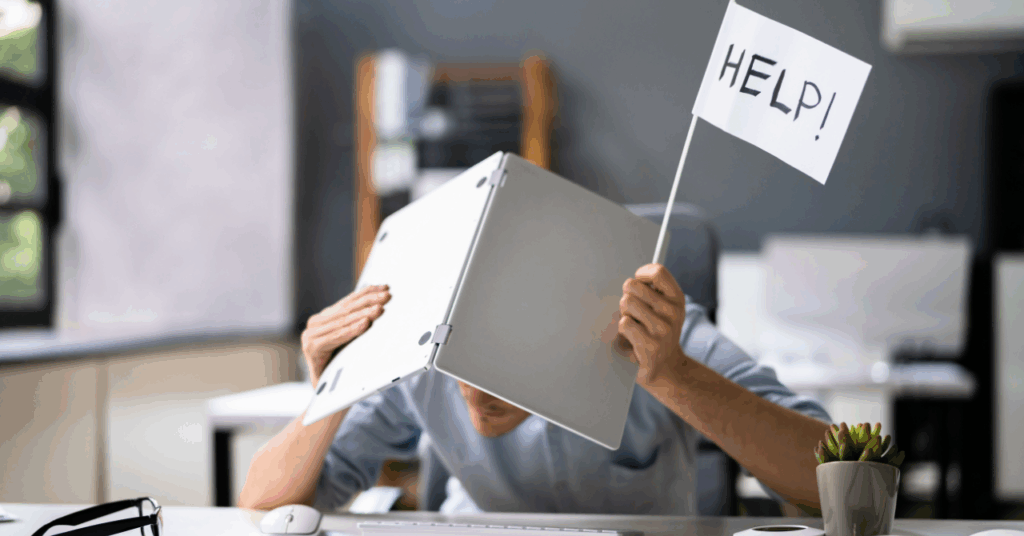
なぜ属人化が起きるのか?
では、なぜここまで「その人しか分からない」状態が生まれてしまうのでしょうか?
理由はシンプルで、中小製造業に特有の構造や社内文化が背景にあるからです。
ITを一人に任せる構造が生まれやすい
まずひとつは、「たまたま詳しかったから」という理由で、IT関連の業務が一人の社員に集約されがちであること。
社内にITの知識を持つ人が少ない場合、自然と「あの人に全部お願いしよう」となり、それが何年も続くと、もはや誰も口を出せなくなる…というパターンが定着します。
情報共有やマニュアル化が後回しにされる
日々の業務に追われる中で、「マニュアルを整備する」「設定手順を文書に残す」といった作業は後回しになりがちです。特に兼務の場合はなおさらです。
「いつかやろう」「まだ大丈夫」と思っているうちに、気づけばその人の頭の中にしかない状態になってしまいます。
経営層がIT業務を「よく分からないもの」として放置しがち
さらに、経営者や管理職が「ITのことはよく分からないから任せてる」と無関心になってしまうことも、属人化の温床になります。
担当者が困っていても相談できず、業務が密室化。やがて、担当者自身も「自分でやるしかない」と思い込んでしまいます。
📌 こうした背景が積み重なり、「辞められたら何も分からない」状況ができあがってしまうのです。
任せることと、丸投げすることは違います。
今後は、「IT業務の見える化」や「誰でも対応できる体制」を意識していく必要があります。
いますぐできるリスク対策
IT担当が突然辞めたときに困らないようにするには、「仕組み」で備えておくしかありません。
ここでは、今すぐ取り組める現実的な3つの対策をご紹介します。
① 情報の見える化(パスワード・手順・構成図の文書化)
まずは何より、ITまわりの情報を「見える化」することが重要です。
- 各サービスのログインIDやパスワード
- サーバーやネットワークの構成図
- ルーターやNAS、プリンタの設定方法
- よくある問い合わせへの対応フロー
これらをExcelや共有ドキュメントにまとめ、最低限の引き継ぎができる状態にしておきましょう。
理想は、「社内の誰が見てもわかる」レベルまで情報を整えることですが、最初から完璧を目指すと手が止まってしまうので、まずは簡単なチェックリストやフォルダ分けから始めるのが現実的です。
② ベンダー・契約情報のリスト化
意外と見落としがちなのが、契約まわりの情報管理です。
- どのサービスをどの会社から契約しているのか
- 誰が担当窓口か、どのメールアドレスでやり取りしているか
- 契約更新日や支払い方法
これらの情報がIT担当者のメールボックスや記憶の中にしかない場合、引き継ぎミスや支払いトラブルが起きるリスクが高まります。
最近は、クラウド型の「IT資産管理ツール」や「契約管理ツール」も充実しているので、必要に応じて検討してみるのも良いでしょう。
③ 最低限の“代替体制”の準備
情報を整えるだけでなく、万が一のときの代替体制を決めておくことも大切です。
- 社内で誰が一時的に対応するのか
- 外部に相談できる業者や支援先はあるか
- 何があったときに、誰が連絡をとるか
完全にITに詳しくなくても構いません。「このときはこの人に聞く」というだけでも、混乱の回避につながります。
⚠️ 特に中小製造業のように人材リソースが限られている環境では、
「困ってから」ではなく「今のうちにやっておく」が命綱です。
後回しにされがちなITまわりの備えこそ、日常業務を止めないための見えない安全装置として、早めに仕込んでおきましょう。

根本解決としての「外部ITチーム化」
とはいえ、日々の業務に追われる中で、こうした対策をすべて社内でこなすのは正直難しい…という声もあるかと思います。
そこで現実的な解決策として注目されているのが、「外部ITチーム化」という選択肢です。
IT担当を“採用・育成”しないという選択
中小製造業では、IT専任者を採用しても業務範囲が広すぎて負担が大きくなりがちです。
また、育成には時間もコストもかかり、その人が辞めてしまえば結局リセットされてしまいます。
そんな背景から、「そもそも社内で抱えず、外部のチームに任せたほうが安定する」という考え方が広がっています。
「ITおまかせアシスタント」なら、属人化リスクを排除できる
たとえば「ITおまかせアシスタント」のようなサービスを利用すれば、
“人”ではなく“仕組み”としてのIT体制を導入することができます。
- PCやプリンタの設定・トラブル対応
- セキュリティの見直しや定期診断
- クラウドサービスの契約管理・運用相談
- ベンダーとのやり取り代行
これらを、経験豊富なスタッフがチーム体制で対応してくれるため、特定の誰かに頼りきりになることがなくなります。
導入しやすい料金と明確な対応範囲で安心
「外部に頼むのは高いのでは?」という心配もあるかもしれませんが、
明確な料金体系とプラン設計がされているため、無理なく導入できるのも魅力のひとつです。
むしろ、担当者の退職や業務停止による損失を考えれば、
最初から外部チームと連携しておいた方がコスト面でも安定感があります。
「誰かが辞めても、ITは止まらない」
そんな状態を、外部の力で整える――それが、属人化リスクを根本から解決する一歩になります。
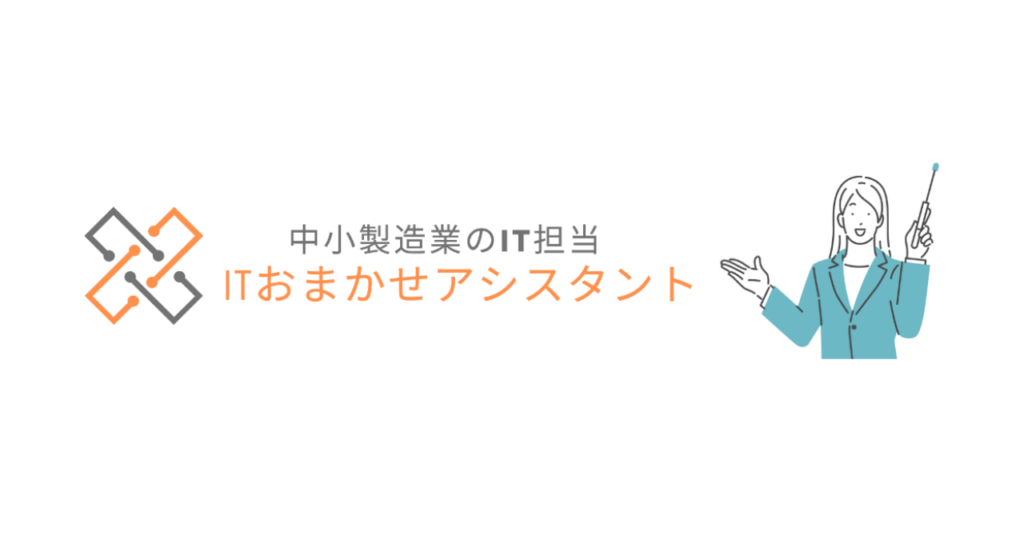
ITの属人化は“明日のリスク”。今すぐできる備えを
IT担当の退職は、いつ起きるかわかりません。
そしてそのときに、「あの人しかわからなかった…」では済まない事態が起きる可能性もあります。
特に中小製造業のような少人数体制では、たった一人の退職が業務全体に大きな影響を及ぼすことも珍しくありません。
だからこそ今、「採用して何とかする」よりも、
「仕組みとして支える体制」を組み込んでおくことが求められています。
情報の見える化、契約の整理、代替要員の準備。
そして、外部サービスとの連携によって、
「辞められても困らない」体制づくりを始めてみてはいかがでしょうか。
「ITおまかせアシスタント」では、貴社の状況に合わせて、無理のないスタートをご提案いたします。
ちょっとした不安、現状の整理、料金のことまで、どんなことでもお気軽にお尋ねください。